これも「がん難民」の一因か
『「がんと闘うべきか否か」について
患者よ、がんと賢く闘え(その3)』
患者よ、がんと賢く闘え(その3)』
北海道がんセンター
名誉院長 西尾 正道
7 医学界の体質と医学教育の問題
日本の医学学会の発表は、経験的で科学的根拠に乏しい発表が多く、お互いが妥協的で、見解の相違でまかり通る雰囲気があるのも事実である。医療は技術的側面を持つために経験が優先されがちな領域であり、医師は本気で自分は正しい治療を行っていると考えているからである。
1968年に行われた和田心臓移植に携わった医師達は、全員が画期的な手術に立ち会えた喜びを語っていたが、決して間違った手術を行ったとは考えていない。刑事訴訟では不起訴となり、医学的には手術の正当性に関して結論を出さないままに推移したため、現在の臓器移植の医療に関しては国際的な遅れをつくりだしている。こうした医学界の曖昧な体質そのものは、現在のがん医療にもその体質を引き継いでおり、現在のがん治療に携わっている医師達は間違っている治療を行っているとは考えておらず、経験の中から学んだがん医療を行っているのである。
しかし人間の経験は限られたものである。特に分化・専門化した現代の医療では、日常の診療は自らが携わった狭い領域での知識と経験で治療法を選択しているのが現実である。日本の外科治療優位の状況は外科医の豊富なマンパワーを背景として、教育の過程や卒後の医療現場環境により培われたものである。“手術したい”“手術したほうがよい”“手術すべきだ”は次元の異なるものであり、また、がんのナチュラルヒストリーを熟知し、resectability(切除できる可能性)とoperability(手術できる可能性)とcurability(治癒できる可能性)の違いを区別して考えるべきである。しかしこれらが混同して外科治療が行われる土壌が問題なのである。
なぜこのような状況になっているのかは、同じがんの局所治療法としての放射線治療が日本ではよく理解されず、有効に利用されていないことが大きな要因の一つと考えられる。切らずに治す放射線治療が普及していなければ、外科的切除しか道はないのである。
表3は日米の放射線治療部門の比較である。米国ではがん患者の約半数の約50万人にがん治療の過程で放射線治療が行われている。一方、日本の利用率は20%以下であり、放射線治療の専門医も少なく、治療機器設置病院の約6割が非常勤医師に頼っている現状である。物理学的な治療精度を維持するための放射線物理士などの職種も院内には確保されていない。その上、多くの医師は、放射線治療は末期がんや他に治療法がなくなった時に紹介するような印象しか持ち合わせていない。高額な整備投資を必要とする割には、診療報酬は低く、そのため非採算部門となり放射線治療は普及せず、「安かろう悪かろう」となっている。
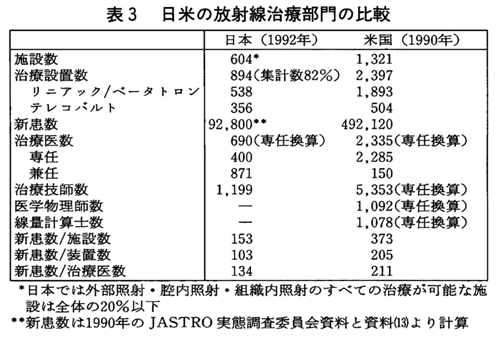
また放射線治療医が育ちにくい大学病院の教育にも問題がある。放射線科の教授が診断学を専門にしていれば、がん患者の診療には不慣れであるが、現在の日本の大学病院の放射線科の80%以上は診断学の専門家であり、放射線治療の専門家は少ない。放射線を使用するという共通性はあっても、放射線診断と放射線治療は全く異質の日常業務の内容である。にもかかわらずこのような体制であれば、大学病院という体質上、放射線治療学の教育は十分とは言えず、放射線治療医が育たないばかりか、関連各科の医師も放射線治療に関して学び、理解することは非常に難しくなる。こうした現状で放射線治療が普及せず、手術優位の治療法が選択され、効果の少ない抗がん剤の治療がはびこる事態となっている。
バランスのとれたがん治療には放射線治療の普及が必須であり、そのためには欧米の先進諸国のように、大学教育において放射線科を診断学と治療学に分け、治療学の独立講座の開設が望まれる。がん医療の揺らぎの最大の原因はがん医療を担う医師の質の問題であり、がん治療専門医の育成環境の貧困な状態は、医学教育の問題点として再検討されるべきである。また高額な治療機器の適正配置と有効利用に関して行政的視点からの検討も必要である。
8 未熟なインフォームド・コンセントの問題
米国は医療行為も契約関係の中で行われているような国であるが、パターナリズムと“あうんの呼吸”で医療を行ってきた日本に、この風潮が急激に入り込み未熟なインフォームド・コンセント(IC)のために医療現場に少なからず混乱を引き起こしたのは事実であろう。最近、ICは医療行為の一部であるという認識が定着しつつある。本来ICは病名の告知を前提として成立するが、がん治療の場合は「がんの告知」という難しい問題がある。同じがん患者でも治癒が期待できる症例から、終末期の症例まで様々であり、積極的に告知して治療法を了解してもらえばよいということでもない。
近代医学の進歩は、生理学的方法論から出発し、化学的方法論・物理学的方法論を経て、疾患の病因論的研究の歴史であったが、QOLの視点を加味した最近の医学は患者の社会性を考慮した生態学的方法論による医療である。患者や家族は一般論としてのICではなく、生態学的視点で個別にQOLを考慮した対応を求めている。
QOLを重視したがん治療は、どのように生きるか、どのような死を迎えるかという人間学や人生学に通じるものであり、円滑な医師・患者関係が成立するためには、医師は各種のがん治療法を熟知し、人間性豊かな深みのある人物であることすら要求されている。しかしこれは決して容易ではない。とりあえずは各医療場面で、誠意を尽くしてできる限りの医療を行うことにより、医療側と患者・家族が気持ちの上でお互いに折り合いをつけるしかないのであるが、医学的知識は専門家として各種治療法を習得している必要がある。悲しいことに、人間は培われた経験や置かれた立場により、その枠内でしかなかなか判断しないものである。
近藤誠氏が温存療法可能なホルモン依存性の「ゆっくりがん」である早期乳がんの治療経験から、「がんもどき」の発想を思いついたり、私が年間約700人のがん患者の診療においてほとんどが進行がんや再発がんである現実からは「がんもどき」は稀であるという認識を持つのは、史的唯物論的な認識の形成過程の典型であろう。
図4は食道がんの治療法の選択に関するSurrogate Surveyによる全国集計の結果である。60歳の男性で胸部中部食道に長径3cmの腫瘍をもったT1N0の早期食道がん症例の場合、どのような治療法を選択するかを、106人の食道疾患研究会の外科医と、84人の放射線治療医にアンケート調査した回答結果である(7)。その結果では、外科医の98%は外科治療を選択し、放射線科医の69%は放射線治療を選択していた。日本の外科医は基本的には早期の食道がんでも切除の方向で考えており、放射線治療を有効に利用する姿勢は乏しく、放射線治療が最もその長所を発揮するT1例ですら手術が選択されているのである。
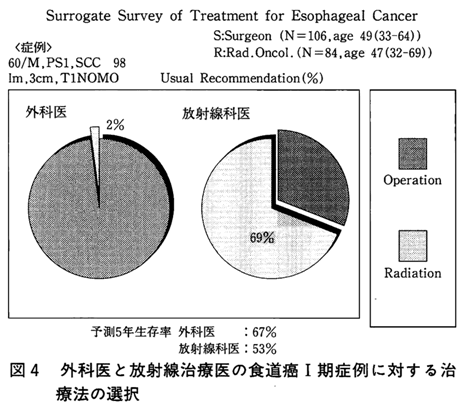
これはICにおいて、放射線治療が十分に説明されていないことによるものと考えられるが、また教育課程で、外科腫瘍学は会得していても、臨床腫瘍学的知識の会得は十分ではないことが窺われる。ちなみに図5は当科で治療した胸部食道扁平上皮がんのT1症例の治療成績である。T1症例は20年間に放射線治療した878例のうち20例しかおらず、本邦ではいかに手術優位の治療法が選択されているかがうかがわれる。また全身状態から手術非適応の症例が多いため、食道がんは照射により治癒状態であっても、他病死する症例も多く、5年累積生存率は57%であるが、他病死を補正した5年原病生存率は93%であり、手術成績と比較して遜色ないものである。このようなデータがある以上、各種治療法の長所を理解しバランス良く説明が行われるべきであるが、己れの専門とする治療法を説明するだけのICでは医療に対する揺らぎが生じるのは当然であろう。
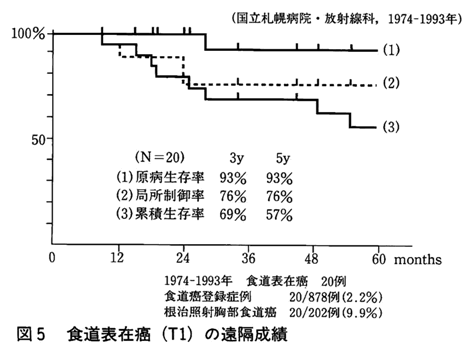
医療の原点は疾患を治癒させ、患者の社会的人間存在の確保にある。しかしがん医療のように助かる患者と、死により人生の中断を余儀なくされる患者が混在している医療においては、患者本人の意思を最大限尊重しつつ、個別の対応が必要であることは論をまたない。昨今は、治療成績は頭打ちとなり、これ以上の生存率の向上が期待できなくなって、同じ治すならQOLが課題となっている。QOLを重視した医療は、生きゆく患者には生きざまを、死に逝く患者には死にざまを考えた医療である。医療行為におけるICにおいては、多種多様な価値観・人生観を持った患者各人の要求を考慮しつつ、専門的医学知識を持った医療従事者が最も適切な治療法の選択を示唆して、医療選択の決定において患者にも関与させ、お互いに折り合いをつけて納得のいく医療を行うことである。
そして最も適切な治療法の選択に当たっては各種治療法の相対的な位置付けが吟味され、各科の専門的医療技術がバランス良く正当に行使されるべきである。この意味でも各科医師は自らが関わっている治療法に固執することなく、各治療法を説明することが望まれる。できれば、厚生省レベルや日本癌治療学会などが指導して、各部位別のがん治療に関する統一したState of the Arts(現在の標準的な考え方)を小冊子などで示し、広報活動(疾患に対する知識と治療法・成績に関する情報提供)をすべきである。それにより、行われる治療が、1治験と2臨床比較試験と3標準治療と4各医師の裁量による個別の治療、の区別が明確となり、患者も治療の位置付けが理解しやすくなるであろう。ただしこうした医療は、患者側にも自己決定しえる主体性と知識が必要であり、患者も賢くなることが要求される。
9 最後に
基本的にがんの治癒のチャンスはonly one chanceである。一度再発や転移が生ずれば、治癒させることは困難なことが多く、したがってがんの一次治療は専門病院で行われるべきである。がんに携わる医師は手術・放射線・化学療法の全ての領域に精通した医師であるべきであり、集学的治療が行われている昨今ではなおさらそうした臨床腫瘍学のための医学教育体制が確立されるべきである。
また科学性を持った医療の維持には、物事を科学的に証明するための比較試験(くじ引き試験)がより必要になる。臨床比較試験に当たっては、医療供給側は、倫理的節度ある臨床の範囲内で、科学的・医学的論理性と合理性を保つべきであり、最近では厚生省や国立がんセンターを中心としてガイドラインも整備されつつある。そして医療を受ける側もモルモット代わりにされるという感性的嫌悪感を捨てて、冷静に臨床比較試験へ理解を持つべきである。この問題は科学や医学と生命倫理の接点となる問題である。
効率優先で、遺伝子の組み替えにより立てないほど太らせた豚を飼育する食肉産業にも、生命倫理の問題が入り込んでいる時代である。生命倫理も超時代的なものではない以上、経済活動と関連した時、別の問題が生じる。真実や倫理性で成り立っているがごとくみえる医科学研究の方向性も、現実にはどの時代においても、社会的・経済的な規定性を帯びながら進歩している。したがって、研究者は経済体制の下部構造の上に、その研究成果を上部構造として積み上げざるを得ないという宿命的構造的矛盾を引き摺りながら、「科学の持つ階級性や経済性」を人間としての倫理的歯止めで、補正しながら歩まざるを得ない。その時、大きな間違いをしないためには、生命倫理の再検討も科学を相対化して考える視点が必要である。
医療に携わる個々人の努力には限界があり、貧困な医療現場環境は情報の貧困を生み、医療の揺らぎを醸成する。待ち時間3時間で、診察時間3分の日本の医療は、個々の患者さんに接する絶対的な情報交換のための時間的保証がなされている医療体制ではない。
表4は米国の代表的ながん専門病院であるM.D.Anderson病院と、日本の中でも比較的恵まれた条件にある大学病院の比較を示したものである。このマンパワーを比較すれば、米国の医療費が高額になる理由もわかる反面、日本は貧困な環境の中で、現場の矛盾を個人の努力や犠牲で吸収しているといえよう。
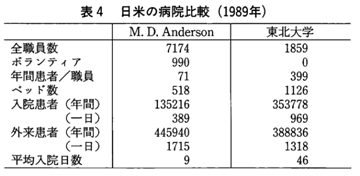
1995年度の国民医療費は27兆円を超え、赤ん坊からお年寄りまでを含む国民一人当たり平均で年間約22万円を医療費として支出し、その額が毎年約1万円ずつ増加している。しかし死因の28%を占めるがんの治療に使われる医療費は、総医療費のわずか8%弱である。高齢化社会に拍車が掛かり、医療費の抑制が社会全体として検討されているが、現在の医療の揺らぎの解決のためには、がん以外の長期的な慢性疾患の診療体制もその在り方が問われるべきであろう。
近藤氏の提起した色々ながん医療の問題は、現場では多かれ少なかれ真剣にがん治療に従事している医師は抱いている問題であり、せっかくのチャンスであるから、国民全体のコンセンサスが得られるようながん医療のあり方について、徹底的に討論されることが望まれる。私も同じ放射線治療医で、近藤氏とは親交もあり、日本の現状のがん医療の在り方について同意する点も多いが、がん医療の根幹に関わる点についてはあえて反論した。
この稿では、放射線治療の立場を中心に論を進めたが、今後は近藤氏の提起した問題について、関連した医学学会内部での専門家同志のシビアな議論の展開が望まれるし、納得のいく結論が出されることを期待したい。和田心臓移植に対して医学的結論を出しえなかった医学界の失敗を繰り返してはならないのである。そして時代の流れに遅蒔きながらついてくる行政側も、薬害エイズ問題への対応のように、重い腰を上げて、バランスの取れたがん医療行政に取り組んでほしいものである。
最後に日本のがん医療はまだまだ整備されている訳ではなく、「医者選びも寿命のうち」であったり、「QOLも医者次第」という要素はあるが、それも長い人生の中での不公平な出会いの一部である。生きるための闘いがあるのだから、死ぬための闘いもあってもよいであろう。「がんと闘う」もよし、「がん前逃亡」もよし、であるが、大事な点は、死を運命づけられている人間という生物が、「悔いのない、納得した死」をどのように迎えることができるかである。そうである以上、戦略・戦術はどうであれ、私は、「患者よ、がんと闘え」と結論し、かつ「賢く、闘え」と叫び稿を終わる。
日本の医学学会の発表は、経験的で科学的根拠に乏しい発表が多く、お互いが妥協的で、見解の相違でまかり通る雰囲気があるのも事実である。医療は技術的側面を持つために経験が優先されがちな領域であり、医師は本気で自分は正しい治療を行っていると考えているからである。
1968年に行われた和田心臓移植に携わった医師達は、全員が画期的な手術に立ち会えた喜びを語っていたが、決して間違った手術を行ったとは考えていない。刑事訴訟では不起訴となり、医学的には手術の正当性に関して結論を出さないままに推移したため、現在の臓器移植の医療に関しては国際的な遅れをつくりだしている。こうした医学界の曖昧な体質そのものは、現在のがん医療にもその体質を引き継いでおり、現在のがん治療に携わっている医師達は間違っている治療を行っているとは考えておらず、経験の中から学んだがん医療を行っているのである。
しかし人間の経験は限られたものである。特に分化・専門化した現代の医療では、日常の診療は自らが携わった狭い領域での知識と経験で治療法を選択しているのが現実である。日本の外科治療優位の状況は外科医の豊富なマンパワーを背景として、教育の過程や卒後の医療現場環境により培われたものである。“手術したい”“手術したほうがよい”“手術すべきだ”は次元の異なるものであり、また、がんのナチュラルヒストリーを熟知し、resectability(切除できる可能性)とoperability(手術できる可能性)とcurability(治癒できる可能性)の違いを区別して考えるべきである。しかしこれらが混同して外科治療が行われる土壌が問題なのである。
なぜこのような状況になっているのかは、同じがんの局所治療法としての放射線治療が日本ではよく理解されず、有効に利用されていないことが大きな要因の一つと考えられる。切らずに治す放射線治療が普及していなければ、外科的切除しか道はないのである。
表3は日米の放射線治療部門の比較である。米国ではがん患者の約半数の約50万人にがん治療の過程で放射線治療が行われている。一方、日本の利用率は20%以下であり、放射線治療の専門医も少なく、治療機器設置病院の約6割が非常勤医師に頼っている現状である。物理学的な治療精度を維持するための放射線物理士などの職種も院内には確保されていない。その上、多くの医師は、放射線治療は末期がんや他に治療法がなくなった時に紹介するような印象しか持ち合わせていない。高額な整備投資を必要とする割には、診療報酬は低く、そのため非採算部門となり放射線治療は普及せず、「安かろう悪かろう」となっている。
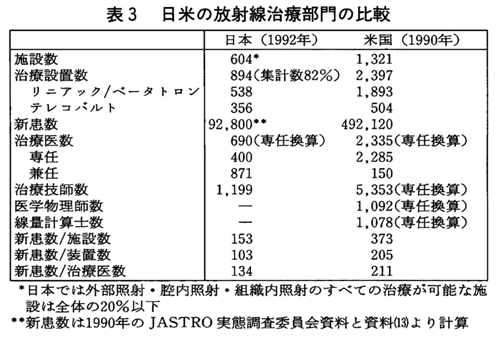
また放射線治療医が育ちにくい大学病院の教育にも問題がある。放射線科の教授が診断学を専門にしていれば、がん患者の診療には不慣れであるが、現在の日本の大学病院の放射線科の80%以上は診断学の専門家であり、放射線治療の専門家は少ない。放射線を使用するという共通性はあっても、放射線診断と放射線治療は全く異質の日常業務の内容である。にもかかわらずこのような体制であれば、大学病院という体質上、放射線治療学の教育は十分とは言えず、放射線治療医が育たないばかりか、関連各科の医師も放射線治療に関して学び、理解することは非常に難しくなる。こうした現状で放射線治療が普及せず、手術優位の治療法が選択され、効果の少ない抗がん剤の治療がはびこる事態となっている。
バランスのとれたがん治療には放射線治療の普及が必須であり、そのためには欧米の先進諸国のように、大学教育において放射線科を診断学と治療学に分け、治療学の独立講座の開設が望まれる。がん医療の揺らぎの最大の原因はがん医療を担う医師の質の問題であり、がん治療専門医の育成環境の貧困な状態は、医学教育の問題点として再検討されるべきである。また高額な治療機器の適正配置と有効利用に関して行政的視点からの検討も必要である。
8 未熟なインフォームド・コンセントの問題
米国は医療行為も契約関係の中で行われているような国であるが、パターナリズムと“あうんの呼吸”で医療を行ってきた日本に、この風潮が急激に入り込み未熟なインフォームド・コンセント(IC)のために医療現場に少なからず混乱を引き起こしたのは事実であろう。最近、ICは医療行為の一部であるという認識が定着しつつある。本来ICは病名の告知を前提として成立するが、がん治療の場合は「がんの告知」という難しい問題がある。同じがん患者でも治癒が期待できる症例から、終末期の症例まで様々であり、積極的に告知して治療法を了解してもらえばよいということでもない。
近代医学の進歩は、生理学的方法論から出発し、化学的方法論・物理学的方法論を経て、疾患の病因論的研究の歴史であったが、QOLの視点を加味した最近の医学は患者の社会性を考慮した生態学的方法論による医療である。患者や家族は一般論としてのICではなく、生態学的視点で個別にQOLを考慮した対応を求めている。
QOLを重視したがん治療は、どのように生きるか、どのような死を迎えるかという人間学や人生学に通じるものであり、円滑な医師・患者関係が成立するためには、医師は各種のがん治療法を熟知し、人間性豊かな深みのある人物であることすら要求されている。しかしこれは決して容易ではない。とりあえずは各医療場面で、誠意を尽くしてできる限りの医療を行うことにより、医療側と患者・家族が気持ちの上でお互いに折り合いをつけるしかないのであるが、医学的知識は専門家として各種治療法を習得している必要がある。悲しいことに、人間は培われた経験や置かれた立場により、その枠内でしかなかなか判断しないものである。
近藤誠氏が温存療法可能なホルモン依存性の「ゆっくりがん」である早期乳がんの治療経験から、「がんもどき」の発想を思いついたり、私が年間約700人のがん患者の診療においてほとんどが進行がんや再発がんである現実からは「がんもどき」は稀であるという認識を持つのは、史的唯物論的な認識の形成過程の典型であろう。
図4は食道がんの治療法の選択に関するSurrogate Surveyによる全国集計の結果である。60歳の男性で胸部中部食道に長径3cmの腫瘍をもったT1N0の早期食道がん症例の場合、どのような治療法を選択するかを、106人の食道疾患研究会の外科医と、84人の放射線治療医にアンケート調査した回答結果である(7)。その結果では、外科医の98%は外科治療を選択し、放射線科医の69%は放射線治療を選択していた。日本の外科医は基本的には早期の食道がんでも切除の方向で考えており、放射線治療を有効に利用する姿勢は乏しく、放射線治療が最もその長所を発揮するT1例ですら手術が選択されているのである。
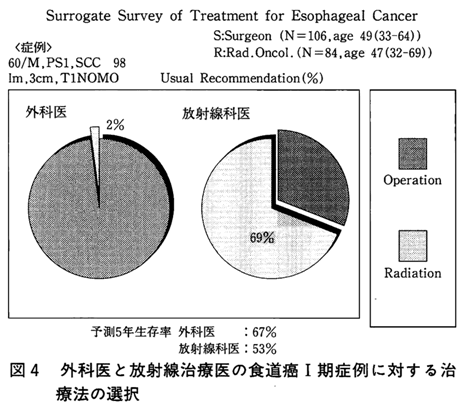
これはICにおいて、放射線治療が十分に説明されていないことによるものと考えられるが、また教育課程で、外科腫瘍学は会得していても、臨床腫瘍学的知識の会得は十分ではないことが窺われる。ちなみに図5は当科で治療した胸部食道扁平上皮がんのT1症例の治療成績である。T1症例は20年間に放射線治療した878例のうち20例しかおらず、本邦ではいかに手術優位の治療法が選択されているかがうかがわれる。また全身状態から手術非適応の症例が多いため、食道がんは照射により治癒状態であっても、他病死する症例も多く、5年累積生存率は57%であるが、他病死を補正した5年原病生存率は93%であり、手術成績と比較して遜色ないものである。このようなデータがある以上、各種治療法の長所を理解しバランス良く説明が行われるべきであるが、己れの専門とする治療法を説明するだけのICでは医療に対する揺らぎが生じるのは当然であろう。
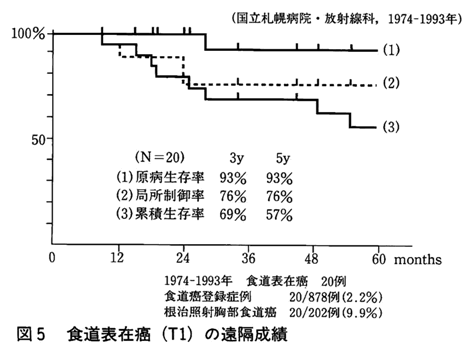
医療の原点は疾患を治癒させ、患者の社会的人間存在の確保にある。しかしがん医療のように助かる患者と、死により人生の中断を余儀なくされる患者が混在している医療においては、患者本人の意思を最大限尊重しつつ、個別の対応が必要であることは論をまたない。昨今は、治療成績は頭打ちとなり、これ以上の生存率の向上が期待できなくなって、同じ治すならQOLが課題となっている。QOLを重視した医療は、生きゆく患者には生きざまを、死に逝く患者には死にざまを考えた医療である。医療行為におけるICにおいては、多種多様な価値観・人生観を持った患者各人の要求を考慮しつつ、専門的医学知識を持った医療従事者が最も適切な治療法の選択を示唆して、医療選択の決定において患者にも関与させ、お互いに折り合いをつけて納得のいく医療を行うことである。
そして最も適切な治療法の選択に当たっては各種治療法の相対的な位置付けが吟味され、各科の専門的医療技術がバランス良く正当に行使されるべきである。この意味でも各科医師は自らが関わっている治療法に固執することなく、各治療法を説明することが望まれる。できれば、厚生省レベルや日本癌治療学会などが指導して、各部位別のがん治療に関する統一したState of the Arts(現在の標準的な考え方)を小冊子などで示し、広報活動(疾患に対する知識と治療法・成績に関する情報提供)をすべきである。それにより、行われる治療が、1治験と2臨床比較試験と3標準治療と4各医師の裁量による個別の治療、の区別が明確となり、患者も治療の位置付けが理解しやすくなるであろう。ただしこうした医療は、患者側にも自己決定しえる主体性と知識が必要であり、患者も賢くなることが要求される。
9 最後に
基本的にがんの治癒のチャンスはonly one chanceである。一度再発や転移が生ずれば、治癒させることは困難なことが多く、したがってがんの一次治療は専門病院で行われるべきである。がんに携わる医師は手術・放射線・化学療法の全ての領域に精通した医師であるべきであり、集学的治療が行われている昨今ではなおさらそうした臨床腫瘍学のための医学教育体制が確立されるべきである。
また科学性を持った医療の維持には、物事を科学的に証明するための比較試験(くじ引き試験)がより必要になる。臨床比較試験に当たっては、医療供給側は、倫理的節度ある臨床の範囲内で、科学的・医学的論理性と合理性を保つべきであり、最近では厚生省や国立がんセンターを中心としてガイドラインも整備されつつある。そして医療を受ける側もモルモット代わりにされるという感性的嫌悪感を捨てて、冷静に臨床比較試験へ理解を持つべきである。この問題は科学や医学と生命倫理の接点となる問題である。
効率優先で、遺伝子の組み替えにより立てないほど太らせた豚を飼育する食肉産業にも、生命倫理の問題が入り込んでいる時代である。生命倫理も超時代的なものではない以上、経済活動と関連した時、別の問題が生じる。真実や倫理性で成り立っているがごとくみえる医科学研究の方向性も、現実にはどの時代においても、社会的・経済的な規定性を帯びながら進歩している。したがって、研究者は経済体制の下部構造の上に、その研究成果を上部構造として積み上げざるを得ないという宿命的構造的矛盾を引き摺りながら、「科学の持つ階級性や経済性」を人間としての倫理的歯止めで、補正しながら歩まざるを得ない。その時、大きな間違いをしないためには、生命倫理の再検討も科学を相対化して考える視点が必要である。
医療に携わる個々人の努力には限界があり、貧困な医療現場環境は情報の貧困を生み、医療の揺らぎを醸成する。待ち時間3時間で、診察時間3分の日本の医療は、個々の患者さんに接する絶対的な情報交換のための時間的保証がなされている医療体制ではない。
表4は米国の代表的ながん専門病院であるM.D.Anderson病院と、日本の中でも比較的恵まれた条件にある大学病院の比較を示したものである。このマンパワーを比較すれば、米国の医療費が高額になる理由もわかる反面、日本は貧困な環境の中で、現場の矛盾を個人の努力や犠牲で吸収しているといえよう。
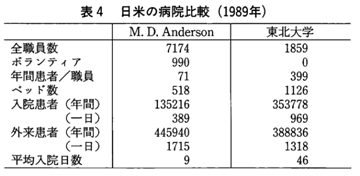
1995年度の国民医療費は27兆円を超え、赤ん坊からお年寄りまでを含む国民一人当たり平均で年間約22万円を医療費として支出し、その額が毎年約1万円ずつ増加している。しかし死因の28%を占めるがんの治療に使われる医療費は、総医療費のわずか8%弱である。高齢化社会に拍車が掛かり、医療費の抑制が社会全体として検討されているが、現在の医療の揺らぎの解決のためには、がん以外の長期的な慢性疾患の診療体制もその在り方が問われるべきであろう。
近藤氏の提起した色々ながん医療の問題は、現場では多かれ少なかれ真剣にがん治療に従事している医師は抱いている問題であり、せっかくのチャンスであるから、国民全体のコンセンサスが得られるようながん医療のあり方について、徹底的に討論されることが望まれる。私も同じ放射線治療医で、近藤氏とは親交もあり、日本の現状のがん医療の在り方について同意する点も多いが、がん医療の根幹に関わる点についてはあえて反論した。
この稿では、放射線治療の立場を中心に論を進めたが、今後は近藤氏の提起した問題について、関連した医学学会内部での専門家同志のシビアな議論の展開が望まれるし、納得のいく結論が出されることを期待したい。和田心臓移植に対して医学的結論を出しえなかった医学界の失敗を繰り返してはならないのである。そして時代の流れに遅蒔きながらついてくる行政側も、薬害エイズ問題への対応のように、重い腰を上げて、バランスの取れたがん医療行政に取り組んでほしいものである。
最後に日本のがん医療はまだまだ整備されている訳ではなく、「医者選びも寿命のうち」であったり、「QOLも医者次第」という要素はあるが、それも長い人生の中での不公平な出会いの一部である。生きるための闘いがあるのだから、死ぬための闘いもあってもよいであろう。「がんと闘う」もよし、「がん前逃亡」もよし、であるが、大事な点は、死を運命づけられている人間という生物が、「悔いのない、納得した死」をどのように迎えることができるかである。そうである以上、戦略・戦術はどうであれ、私は、「患者よ、がんと闘え」と結論し、かつ「賢く、闘え」と叫び稿を終わる。
文献
1 近藤 誠:患者よ、がんと闘うな。文芸春秋、1996.
2 Charles S.Fuchs,et al:Gastric Carcinoma.N.Engl.J.Med.333(1):32-41,1995.
3 「表在癌」アンケート集計報告。第49回食道疾患研究会、大津市、1995年
4 西尾正道、他:非切除小細胞癌に対する集学的治療―Palliative careとしての放射線療法―。日本肺癌学会ワークショップ第10回記念講演集―肺癌に対する集学的治療は進歩したか―、中山書店:P72-84,1996.
5 第32回ASCO Proceedings, 15:372,1996.
6 西尾正道、他:放射線治療の有用性評価。臨床放射線、Vol.40,No.2,P2345-253,1995.
7 西尾正道、他:Surrogate Surveyによる食道癌治療の全国調査結果。癌の臨床、40:154-160,1994.
8 山田章吾(東北大学放射線科):Personal Communication.
※注「月刊新医療」96年11月号の「特集・揺らぐ日本医療」として掲載されたものである。
著者よりのコメント:
この論文は17年前に書いたものですが、近藤氏の原点は変わっていませんので、対応として手を加えず掲載しました。人生観や価値観が異なる人間が人間を相手にする医療では治療結果が全て満足なものとなることはない。場合によっては治療関連死もある。結果として上手くいかなかった有名人の治療結果をあげつらって極論を述べることはバランスを欠如した姿勢である。医学の素人には通用するが、現場で苦闘している医師は誤魔化されない。近藤氏には医師として学会にも出席して討論する姿勢が望まれる。
2 Charles S.Fuchs,et al:Gastric Carcinoma.N.Engl.J.Med.333(1):32-41,1995.
3 「表在癌」アンケート集計報告。第49回食道疾患研究会、大津市、1995年
4 西尾正道、他:非切除小細胞癌に対する集学的治療―Palliative careとしての放射線療法―。日本肺癌学会ワークショップ第10回記念講演集―肺癌に対する集学的治療は進歩したか―、中山書店:P72-84,1996.
5 第32回ASCO Proceedings, 15:372,1996.
6 西尾正道、他:放射線治療の有用性評価。臨床放射線、Vol.40,No.2,P2345-253,1995.
7 西尾正道、他:Surrogate Surveyによる食道癌治療の全国調査結果。癌の臨床、40:154-160,1994.
8 山田章吾(東北大学放射線科):Personal Communication.
※注「月刊新医療」96年11月号の「特集・揺らぐ日本医療」として掲載されたものである。
著者よりのコメント:
この論文は17年前に書いたものですが、近藤氏の原点は変わっていませんので、対応として手を加えず掲載しました。人生観や価値観が異なる人間が人間を相手にする医療では治療結果が全て満足なものとなることはない。場合によっては治療関連死もある。結果として上手くいかなかった有名人の治療結果をあげつらって極論を述べることはバランスを欠如した姿勢である。医学の素人には通用するが、現場で苦闘している医師は誤魔化されない。近藤氏には医師として学会にも出席して討論する姿勢が望まれる。

患者にとっても様々な医療情報がもたらされ、就中、今回のようなベストセラーになるとかなり多くの人に影響があります。そこで本来は先生の言われるように学会の内部などで率先してシムポジウムなどを開催するなりして納得できる結論を得るか、結論が得られないまでも問題点を整理するぐらいのことはしなければならないと思いますがやらないでしょう。
そこで提案ですが、西尾先生と近藤先生に公開討論会をしていただくことをお願いしたいと思います。
「市民のためのがん治療の会」は、西尾先生と「がん医療についての情報公開」を活動の理念とする会を作ろうということで約10年活動して参りました。「患者にとっての医療情報とは何か」というようなテーマで、10年間のまとめの記念講演会としたいと思います。
近藤先生も「相手のいないところで論評するのは公平を欠く」と言っておられます。近藤先生にもお願いしてみますので、西尾先生、どうぞよろしくお願いいたします。
略歴
西尾 正道(にしお まさみち)
独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 名誉院長 (放射線治療科)
1947年函館市生まれ。1974年札幌医科大学卒業。国立札幌病院・北海道地方がんセンター放射線科に勤務し39年間がんの放射線治療に従事。がんの放射線治療を通じて日本のがん医療の問題点を指摘し、収善するための医療を推進。「市民のためのがん治療の会」代表協力医を10年間つとめ本年4月より当会顧問。
独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 名誉院長 (放射線治療科)
1947年函館市生まれ。1974年札幌医科大学卒業。国立札幌病院・北海道地方がんセンター放射線科に勤務し39年間がんの放射線治療に従事。がんの放射線治療を通じて日本のがん医療の問題点を指摘し、収善するための医療を推進。「市民のためのがん治療の会」代表協力医を10年間つとめ本年4月より当会顧問。
