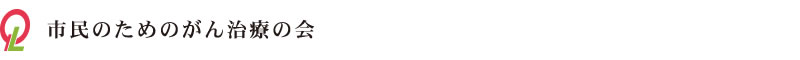告知などしなくても患者自身がインターネットで調べれば予後(余命)を知ることができる今。だが患者は「生きたい」と思い続ける。その患者の心に寄り添える医療者であって欲しい。
『短い命を告げられるがん患者さん』
がん・感染症センター都立駒込病院
院長 佐々木 常雄
院長 佐々木 常雄
<あと3ヶ月の命と言われました>
この7、8年ほど前から「セカンド・オピニオン」が普及し、私の外来にもたくさんのがん患者さんが相談に来られます。
私が化学療法を専門としていることもあってか、最近は「もう化学療法はありません、あと3ヶ月の命と言われました」そう言われて、涙、涙で来られる患者さんは多いのです。
私が医師になった頃は、患者さん本人にはがんという病名を隠しました。たとえ患者さんが医師であっても隠すことがありました。今では考えられないことですが、医師が進行した胃がんになって手術した場合、手術後に麻酔からさめた医師である患者本人に、「ほら、がんでなくて良かったですね」と、同じ日に手術をした胃潰瘍の患者さんの切除した胃を見せたりしたのです。そして、本人に見せるカルテと本物のカルテと2重に作ったりしました。
がんは死と直結していると考える時代で、がんであることを、そして、病状が悪くなっても、死を最期まで徹底して隠しました。「あなたが死ぬ」なんて、そんな残酷なことを絶対に言えない、医師は患者さんに対して「愛とおもいやり」のために死を知らせない、医療者も家族も、患者さん本人に対しては、がんを隠すこと、死を隠すことが、最大限よかれと思って、「最大の愛とおもいやり」であると信じていたのです。
がん治療は発展しました。がんが治る方も多くなりました。しかし、あれから30年余り経っても、2人にひとりはがんになり、3人にひとりはがんで亡くなるのです。 日本人の死因の第一位が、がんであることに変りないのですが、最近は「もう、治療法はありません」「あと3ヶ月の命と思ってください」「今のうちに旅行にでも行ったらどうですか?」「紹介状書きますから、好きな病院へ行っていいですよ」と、さらには「人間の命が限られていることが分からないのですか?」「そんなに命に未練があるのですか?」「2年生きられたからいいじゃないですか」、、、、等々、そう主治医から言われて、涙、涙で来られる患者さんが絶えないのです。
日本人の倫理感は変わってしまったのでしょうか?
日本人は、そう言われても、大丈夫になったのでしょうか?
私が医師になった頃は、患者さん本人にはがんという病名を隠しました。たとえ患者さんが医師であっても隠すことがありました。今では考えられないことですが、医師が進行した胃がんになって手術した場合、手術後に麻酔からさめた医師である患者本人に、「ほら、がんでなくて良かったですね」と、同じ日に手術をした胃潰瘍の患者さんの切除した胃を見せたりしたのです。そして、本人に見せるカルテと本物のカルテと2重に作ったりしました。
がんは死と直結していると考える時代で、がんであることを、そして、病状が悪くなっても、死を最期まで徹底して隠しました。「あなたが死ぬ」なんて、そんな残酷なことを絶対に言えない、医師は患者さんに対して「愛とおもいやり」のために死を知らせない、医療者も家族も、患者さん本人に対しては、がんを隠すこと、死を隠すことが、最大限よかれと思って、「最大の愛とおもいやり」であると信じていたのです。
がん治療は発展しました。がんが治る方も多くなりました。しかし、あれから30年余り経っても、2人にひとりはがんになり、3人にひとりはがんで亡くなるのです。 日本人の死因の第一位が、がんであることに変りないのですが、最近は「もう、治療法はありません」「あと3ヶ月の命と思ってください」「今のうちに旅行にでも行ったらどうですか?」「紹介状書きますから、好きな病院へ行っていいですよ」と、さらには「人間の命が限られていることが分からないのですか?」「そんなに命に未練があるのですか?」「2年生きられたからいいじゃないですか」、、、、等々、そう主治医から言われて、涙、涙で来られる患者さんが絶えないのです。
日本人の倫理感は変わってしまったのでしょうか?
日本人は、そう言われても、大丈夫になったのでしょうか?
<有名な医師は、「命に限りがあることを知るべきだ」と言う>
ある有名な医師は「患者はもっと、がんの勉強をすべきだ。終末期になっても、まだ治療法があるのではないか? もっと治療して欲しいと諦めが悪い。人間の命は限られていることを患者はもっと自覚すべきだ。人間の死を考えるべきだ、命に限りがあることを知るべきだ」と言います。今の社会を超高齢化社会、さらには多死社会と言うのだそうですが、私は、何か、かけがえのない、大切な命が「あきらめろ、あきらめろ」と言われているような気がするのです。
ある医師は、「現代人は、人の死に会うことが少ないから、死を直視する会」を考え、死に直面しても大丈夫なように「死を直視する機会を持ち、各自の生きがいを追求することで、幸せになることを支援する地域ぐるみの教育を目指しています」といいます。
しかし、元気な時に、死の教育を受けて、悟ったと思っていても、実際に自分自身が「死に直面した時」は、そんな悟りは吹っ飛んでしまった患者さんを、私はたくさん知っているのです。たとえば、医療者が、どんなに他人の死を看取っていても、どんなに他人の死に直面しても、所詮は他人の死なのです。自分の死とは違うのです。
元気な時に、他人の死を見たり、死の教育を受けることは、命の大切さを知るためには大事なことと思うのですが、しかし、自分が死に直面した時は、死の恐怖を前にして、それは単なる知識でしかなくなるのだと思います。
これまで、患者さんが、どれだけ良き人生を歩んできたにしても、がんが進行し、短い命の宣告で奈落に落され、死の恐怖におののきながら暗い沈んだ表情で来られる方に会うと、20世紀の、病気を知らされないまま、死を自覚しないまま、隠されたまま死んだ時代のほうが良かったのではないか、あの時代の方が優しさがあったのではないかと思うほどです。
しかし、もう、短い命であることを知らないで、知らされないでおれる時代ではなくなりました。ラ・ロシュフコーは、「人間は、太陽と死を直視出来ない」と言ったそうです。でも、そんなことは、もう言っていられません。20世紀の「死を隠す、患者さんに真実を隠す」時代には戻れないのです。たとえ、医師が患者さんの予後(余命)を隠したとしても、患者自身がインターネットで調べればすぐに分かる時代なのです。
私は、20世紀の時のように、最後まで治療するようにと、死の間際まで抗がん剤治療をする時代に戻せと言っているのではありません。患者さんの「生きたい」という人間として当然のことを理解する心を持って欲しいのです。患者さんの「生きたい」という心に寄り添える医療者であって欲しいのです。
ある医師は、「現代人は、人の死に会うことが少ないから、死を直視する会」を考え、死に直面しても大丈夫なように「死を直視する機会を持ち、各自の生きがいを追求することで、幸せになることを支援する地域ぐるみの教育を目指しています」といいます。
しかし、元気な時に、死の教育を受けて、悟ったと思っていても、実際に自分自身が「死に直面した時」は、そんな悟りは吹っ飛んでしまった患者さんを、私はたくさん知っているのです。たとえば、医療者が、どんなに他人の死を看取っていても、どんなに他人の死に直面しても、所詮は他人の死なのです。自分の死とは違うのです。
元気な時に、他人の死を見たり、死の教育を受けることは、命の大切さを知るためには大事なことと思うのですが、しかし、自分が死に直面した時は、死の恐怖を前にして、それは単なる知識でしかなくなるのだと思います。
これまで、患者さんが、どれだけ良き人生を歩んできたにしても、がんが進行し、短い命の宣告で奈落に落され、死の恐怖におののきながら暗い沈んだ表情で来られる方に会うと、20世紀の、病気を知らされないまま、死を自覚しないまま、隠されたまま死んだ時代のほうが良かったのではないか、あの時代の方が優しさがあったのではないかと思うほどです。
しかし、もう、短い命であることを知らないで、知らされないでおれる時代ではなくなりました。ラ・ロシュフコーは、「人間は、太陽と死を直視出来ない」と言ったそうです。でも、そんなことは、もう言っていられません。20世紀の「死を隠す、患者さんに真実を隠す」時代には戻れないのです。たとえ、医師が患者さんの予後(余命)を隠したとしても、患者自身がインターネットで調べればすぐに分かる時代なのです。
私は、20世紀の時のように、最後まで治療するようにと、死の間際まで抗がん剤治療をする時代に戻せと言っているのではありません。患者さんの「生きたい」という人間として当然のことを理解する心を持って欲しいのです。患者さんの「生きたい」という心に寄り添える医療者であって欲しいのです。
<標準化学療法を示す、ガイドライン時代>
20世紀の後半は、がんという病名を告知していても、そして、治療法がなくなっても、「もう治療法はありません」とは言わない時代でした。
「いま、体調が悪いので、体力がつくまで待ちましょう。いま、体がきついので、抗がん剤を少量でやってみましょう」と言って希望を持たせました。休眠療法などと言って、抗がん剤少量投与法が流行った時代でもありました。確かに少量でも効いた患者さんはいたのです。
21世紀に入って、患者の権利として、知る権利、自分で治療を選ぶ自己決定権、セカンド・オピニオンとして他の病院で確かめる検証権等が当然の時代となりました。これらのことは患者の権利章典として病院の玄関に掲げられました。
がんに関する学会では、がんの治療ガイドラインを作り、標準治療を示しました。私もその作成にあたりました。標準治療を患者自身が知りたい、そして知る。 厚生労働省は日本のどこでも、誰でも、標準治療が受けられることを目標としました。
標準治療を患者さん自身が知りたい、そして知る。患者さんは、標準治療を受け、それから標準治療が効かなくなった場合、死が近いことを告げられる、死が近いことを知るという時代になったのです。
希望を持ちたくとも、真実を言って欲しくなくとも、ホスピスなんて考えたくなくとも「患者本位の医療、自分で選択する、自己決定権」という御旗の下に、かなり明確に短い命であることを知る、知らされる時代となりました。
「いま、体調が悪いので、体力がつくまで待ちましょう。いま、体がきついので、抗がん剤を少量でやってみましょう」と言って希望を持たせました。休眠療法などと言って、抗がん剤少量投与法が流行った時代でもありました。確かに少量でも効いた患者さんはいたのです。
21世紀に入って、患者の権利として、知る権利、自分で治療を選ぶ自己決定権、セカンド・オピニオンとして他の病院で確かめる検証権等が当然の時代となりました。これらのことは患者の権利章典として病院の玄関に掲げられました。
がんに関する学会では、がんの治療ガイドラインを作り、標準治療を示しました。私もその作成にあたりました。標準治療を患者自身が知りたい、そして知る。 厚生労働省は日本のどこでも、誰でも、標準治療が受けられることを目標としました。
標準治療を患者さん自身が知りたい、そして知る。患者さんは、標準治療を受け、それから標準治療が効かなくなった場合、死が近いことを告げられる、死が近いことを知るという時代になったのです。
希望を持ちたくとも、真実を言って欲しくなくとも、ホスピスなんて考えたくなくとも「患者本位の医療、自分で選択する、自己決定権」という御旗の下に、かなり明確に短い命であることを知る、知らされる時代となりました。
<心は以前よりも苦しくなっているのではないか>
標準治療が効かなくなり、治療法がなくなり、死が直前に迫っていることを知ったがんの患者さんは、宗教なしで、どうすれば安寧な気持ちで過ごせる、生きられるのであろうか? 現代において、あの世を信じることなどは、多くの人は今さら不可能であると思います。現代は、緩和医療の発達で、確かに多くの痛みをコントロールすることが出来るようになりました。死を前にして、痛みが抑えられない時、呼吸が苦しい時、そして、精神的に辛い時には、セデーションと言って、薬で眠ること(持続睡眠)も出来るようになりました。しかし、現代の終末期は、短い命を知らされて、患者さんは本当に、心落ち着いて過ごせているのだろうか?
21世紀に入って、真実を知らされ、死が近いことを知らされて、心は以前よりも苦しくなっているのではないか、と私は考えるのです。
私は、「もう治療法はない、あと3ヶ月の命、あと1ヶ月の命」と言われて、死に直面し、奈落に落とされ、涙ながらに相談に来られる多くの患者さんに会うにつけ、早く安寧な気持ちに戻れる、心静かに過ごせる術を探がさなければと思いました。宗教なしで、死の恐怖を乗り越える術をどうしても知りたいと思いました。
このことを考えているうちに、「科学の発達はたくさんの学問と経験の積み重ねが、引き継がれることによってものすごく発達したのに、人の心は、魂は引き継がれてきたのだろうか?」と思ったのです。
私が担当させていただき、看取らせていただいた患者さんは2000人以上におよびます。多くの患者さんの心、魂は私の心に残っております。そして昔からの先人の魂もたくさん書物に残っています。たくさん悩んで、苦労して、辛い思いをして終末期を過ごした、そして次の時代に託した精神、魂を、私たちは、それをしっかりと、そして今の時代に合うように、うまく受け継いでいるのであろうか? そして、もしかしたら、その中には、終末期になっても安寧に過ごせるヒントがあるのではないかと考えるようになりました。
21世紀に入って、真実を知らされ、死が近いことを知らされて、心は以前よりも苦しくなっているのではないか、と私は考えるのです。
私は、「もう治療法はない、あと3ヶ月の命、あと1ヶ月の命」と言われて、死に直面し、奈落に落とされ、涙ながらに相談に来られる多くの患者さんに会うにつけ、早く安寧な気持ちに戻れる、心静かに過ごせる術を探がさなければと思いました。宗教なしで、死の恐怖を乗り越える術をどうしても知りたいと思いました。
このことを考えているうちに、「科学の発達はたくさんの学問と経験の積み重ねが、引き継がれることによってものすごく発達したのに、人の心は、魂は引き継がれてきたのだろうか?」と思ったのです。
私が担当させていただき、看取らせていただいた患者さんは2000人以上におよびます。多くの患者さんの心、魂は私の心に残っております。そして昔からの先人の魂もたくさん書物に残っています。たくさん悩んで、苦労して、辛い思いをして終末期を過ごした、そして次の時代に託した精神、魂を、私たちは、それをしっかりと、そして今の時代に合うように、うまく受け継いでいるのであろうか? そして、もしかしたら、その中には、終末期になっても安寧に過ごせるヒントがあるのではないかと考えるようになりました。
<エピソード:生きていても何も役に立たない>
67歳女性 Aさんは、10 年前に会社を定年となった夫と2人暮らしでした。 Aさんは右乳がんの手術をしてから3年後に骨に転移が見つかり、その後これまで5年間、B病院で、ホルモン剤、抗がん剤、放射線治療のために入院と退院を繰り返して治療を受けていました。しかし、がんは次第に全身の骨と肝臓にも転移し、寝たきりの状態で、ついには、痛みのために寝返りも出来ない状態となっていました。
ほとんど治療はやり尽くしていましたが、全身の骨への転移による痛みがひどく、モルヒネでもコントロールが難しい状況でした。疼痛緩和のため、骨盤骨への放射線治療を行うために、私たちの病院に転院してきました。これまでB病院での治療の5年間に、主治医は何回も代わったのですが、今回の1ヶ月間の入院では、化学療法の効果も無く、新しい主治医から、AさんとAさんの夫に「もう、治療法はありません。もうB病院ではやることはなくなりました。あと1ヶ月の命と思ってください。」と言われました。
私たちの病院に来られてからは、終末期をたくさん経験しているベテランの医長がAさんの主治医となり、研修医も一緒に診てくれることとなりました。私が最初に外来でAさんの夫から相談を受けていたことと、Aさんに会ってみて、痛みが尋常ではなかったこと、そして暗い暗い表情だったのも気になって、時々病室を訪ねました。
何回か、個室の病室を訪問しているうちに、痛みもすこし和らいだようでしたが、食事は少ししか取れず、暗い表情は変わりませんでした。また、いつもカーテンは閉められ、部屋はいつも暗くしてありました。自分からはあまり話すこともなく、私が体の調子を聞いても、夫に促されてやっと答えてくれる程度でした。
どうしたものだろう、この暗い表情が、どうにか和らぐことは出来ないだろうか? 手と首しか動かせない患者に、そして「あと1ヶ月の命」と言われた患者に、私は何を話せば良いのだろうか? 痛みを止めることは出来ても、この暗い表情を、ただ見守るしか出来ないのだろうか? 私はそう思っていました。
転院して10日くらい経ったある日、病室を訪問した時、いつもと違って窓のカーテンは開けられ、部屋が明るくなっていました。
「先生、心配してくださってありがとうございます。私、動けなくなって、主人や、みんなに迷惑をかけて、でもなんとか、もう一度良くなって帰りたいと思っていました。そうしたら、B病院で、あと1ヶ月の命と言われた時は、心が真っ暗になり、このままもう動けないまま、何も出来ないまま死ぬんだと思いました。何にも役に立たない。生きていても何も役に立たない。皆に迷惑をかけるだけだ。生きている意味がないと思いました。 涙ばかり出て、こんなならポックリと早く死んだ方がよい、みんなに迷惑にならない方がよいと思いました。この病院に連れてこられて、みんな優しくして下さるのですが、気持ちは変わりませんでした。痛みはすこし良くなっても、死ぬのが怖いのに、コトンとこのまま死なせてくれないかしらとも思いました。毎日、病室に通ってくる夫は、いろんな食べ物を買って来てくれるのですが、申し訳程度に、すこしだけ箸をつけていました。実際に、食欲は全くありませんでした。
5日前、そのおかずに手もつけないでいる私に、昔から無口な夫が{君が生きてさえいてくれれば それでいいんだよ。生きていて欲しい。}と言って帰ってゆきました。 その2日後の夜、ふと私は気づきました。毎日通ってくる夫は大変だけど、私が生きていることが、夫には励みになっている。私が生きている意味があるのかもしれない。私が死んだら夫はひとりになってしまう。がんばって生きなきゃ、私が死んだ後の家事を沢山教えなきゃ と思ったのです。こんな私でも役に立つことがあるんだと思ったのです。それから、今日は家事のあれを教えなきゃ、明日はあれを教える、、、と思っているうちに、すこし心が明るくなれたような気がしたのです。寝たきりですが、腕は動くので、痛みの無い時は、夫が後で見てくれるように、役立つように、家事のことをノートに書いているのです。私たちは2人暮らしです。私が死んだら、夫は一人になるのです。」そこまで話してから、にっこりとされたのでした。この話を聞いた私は、心につっかえていたようなものが降りた気がしました。
夫の「君が生きてさえいてくれれば それでいいんだよ。生きていて欲しい」という言葉で、Aさんは「生きている意味を見出すことが出来たのだ」と思いました。あと1ヶ月の命と言われた、その奈落から、夫のその言葉で、這い上がるきっかけとなったのです。Aさんの場合は、ただ仲のいい夫婦愛とか、そのようなことで片付けられる事ではないように思いました。人間は、まったく動けなくなっても、たとえ生きている、その事だけでも人の役に立つことが出来るのだと思いました。
もし自分が、ただ生きているだけ、人に迷惑をかけているだけとしか思えない、そのような場合でも、本人は気づかないかもしれないが、生きている、生きているそのことが他人の心を助け、他人を励ましていることもあるのだ。ひとり暮らしの人でも、誰でも一人で生きているのではない。生きているということは、大切なことなのだ。命はたった一つのかけがえのない、大切なものだということをお教わったように思いました。
ほとんど治療はやり尽くしていましたが、全身の骨への転移による痛みがひどく、モルヒネでもコントロールが難しい状況でした。疼痛緩和のため、骨盤骨への放射線治療を行うために、私たちの病院に転院してきました。これまでB病院での治療の5年間に、主治医は何回も代わったのですが、今回の1ヶ月間の入院では、化学療法の効果も無く、新しい主治医から、AさんとAさんの夫に「もう、治療法はありません。もうB病院ではやることはなくなりました。あと1ヶ月の命と思ってください。」と言われました。
私たちの病院に来られてからは、終末期をたくさん経験しているベテランの医長がAさんの主治医となり、研修医も一緒に診てくれることとなりました。私が最初に外来でAさんの夫から相談を受けていたことと、Aさんに会ってみて、痛みが尋常ではなかったこと、そして暗い暗い表情だったのも気になって、時々病室を訪ねました。
何回か、個室の病室を訪問しているうちに、痛みもすこし和らいだようでしたが、食事は少ししか取れず、暗い表情は変わりませんでした。また、いつもカーテンは閉められ、部屋はいつも暗くしてありました。自分からはあまり話すこともなく、私が体の調子を聞いても、夫に促されてやっと答えてくれる程度でした。
どうしたものだろう、この暗い表情が、どうにか和らぐことは出来ないだろうか? 手と首しか動かせない患者に、そして「あと1ヶ月の命」と言われた患者に、私は何を話せば良いのだろうか? 痛みを止めることは出来ても、この暗い表情を、ただ見守るしか出来ないのだろうか? 私はそう思っていました。
転院して10日くらい経ったある日、病室を訪問した時、いつもと違って窓のカーテンは開けられ、部屋が明るくなっていました。
「先生、心配してくださってありがとうございます。私、動けなくなって、主人や、みんなに迷惑をかけて、でもなんとか、もう一度良くなって帰りたいと思っていました。そうしたら、B病院で、あと1ヶ月の命と言われた時は、心が真っ暗になり、このままもう動けないまま、何も出来ないまま死ぬんだと思いました。何にも役に立たない。生きていても何も役に立たない。皆に迷惑をかけるだけだ。生きている意味がないと思いました。 涙ばかり出て、こんなならポックリと早く死んだ方がよい、みんなに迷惑にならない方がよいと思いました。この病院に連れてこられて、みんな優しくして下さるのですが、気持ちは変わりませんでした。痛みはすこし良くなっても、死ぬのが怖いのに、コトンとこのまま死なせてくれないかしらとも思いました。毎日、病室に通ってくる夫は、いろんな食べ物を買って来てくれるのですが、申し訳程度に、すこしだけ箸をつけていました。実際に、食欲は全くありませんでした。
5日前、そのおかずに手もつけないでいる私に、昔から無口な夫が{君が生きてさえいてくれれば それでいいんだよ。生きていて欲しい。}と言って帰ってゆきました。 その2日後の夜、ふと私は気づきました。毎日通ってくる夫は大変だけど、私が生きていることが、夫には励みになっている。私が生きている意味があるのかもしれない。私が死んだら夫はひとりになってしまう。がんばって生きなきゃ、私が死んだ後の家事を沢山教えなきゃ と思ったのです。こんな私でも役に立つことがあるんだと思ったのです。それから、今日は家事のあれを教えなきゃ、明日はあれを教える、、、と思っているうちに、すこし心が明るくなれたような気がしたのです。寝たきりですが、腕は動くので、痛みの無い時は、夫が後で見てくれるように、役立つように、家事のことをノートに書いているのです。私たちは2人暮らしです。私が死んだら、夫は一人になるのです。」そこまで話してから、にっこりとされたのでした。この話を聞いた私は、心につっかえていたようなものが降りた気がしました。
夫の「君が生きてさえいてくれれば それでいいんだよ。生きていて欲しい」という言葉で、Aさんは「生きている意味を見出すことが出来たのだ」と思いました。あと1ヶ月の命と言われた、その奈落から、夫のその言葉で、這い上がるきっかけとなったのです。Aさんの場合は、ただ仲のいい夫婦愛とか、そのようなことで片付けられる事ではないように思いました。人間は、まったく動けなくなっても、たとえ生きている、その事だけでも人の役に立つことが出来るのだと思いました。
もし自分が、ただ生きているだけ、人に迷惑をかけているだけとしか思えない、そのような場合でも、本人は気づかないかもしれないが、生きている、生きているそのことが他人の心を助け、他人を励ましていることもあるのだ。ひとり暮らしの人でも、誰でも一人で生きているのではない。生きているということは、大切なことなのだ。命はたった一つのかけがえのない、大切なものだということをお教わったように思いました。
<死の恐怖を乗り越える術>
私は、奈落から這い上がれた患者さん方からその心を聞かせていただき、これまで経験させたいただいたたくさんの終末期のエピソードを思い出し、書物による先人の思いを考えているうちに、最近、死に直面して生きるヒント、短い命と言われても心安らかになるためのわずかなヒントが、ごくわずかかもしれませんが、私には少しだけ見えてきたように思えるのです。
死の恐怖の奈落から這い上がった方々から「どうして這い上がれたか?」を聞いているうちに、すこしづつ、分かってきたことがあります。そのひとつは、「まだ、自分は役に立つことがある」と思える人は早く這い上がれるように思いました。
そして、何かは分からないが、何かのきっかけで、奈落から這い上がれる、ということを患者さんから教わりました。そして、次第に、私は「人は誰でも、心の奥に安心できる心があるのだ」と確信を持てるようになってきました(このことは紙面の都合上、一言、二言では書けないのですが、、、)。
病気になれば、人は心が弱くなります。しかし、人はけっして本当に心が弱いのではないのです。なぜなら、心の奥には安心できる心を持っているからです。しかし、残念ながら、その心を引き出せないままの方もおられるのです。
そして、その心の奥にある「安心できる心」をどうにかして、早く引き出せるようにしたいと思いました。
這い上がるためのヒントのひとつは、このような奈落に落ちた患者さんと話す時、医療者や周りの方は「あなたは絶対に這い上がれる」という確信を持っていることが大切であると思いました。
また、ある患者さんから教わったことですが、医療者が医学のデータとして、数ヶ月の命が予想されることを患者さんに言う場合、『大事にされている命だよ』というメッセージが患者さんに伝わることがとても大事であるということでした。
私は、さらに死の恐怖から乗り越えられる「術」を捜しつづけています。そして、わずかなヒントかもしれませんが、少しづつそのわずかなヒントが見つかってきています。
そして、何かは分からないが、何かのきっかけで、奈落から這い上がれる、ということを患者さんから教わりました。そして、次第に、私は「人は誰でも、心の奥に安心できる心があるのだ」と確信を持てるようになってきました(このことは紙面の都合上、一言、二言では書けないのですが、、、)。
病気になれば、人は心が弱くなります。しかし、人はけっして本当に心が弱いのではないのです。なぜなら、心の奥には安心できる心を持っているからです。しかし、残念ながら、その心を引き出せないままの方もおられるのです。
そして、その心の奥にある「安心できる心」をどうにかして、早く引き出せるようにしたいと思いました。
這い上がるためのヒントのひとつは、このような奈落に落ちた患者さんと話す時、医療者や周りの方は「あなたは絶対に這い上がれる」という確信を持っていることが大切であると思いました。
また、ある患者さんから教わったことですが、医療者が医学のデータとして、数ヶ月の命が予想されることを患者さんに言う場合、『大事にされている命だよ』というメッセージが患者さんに伝わることがとても大事であるということでした。
私は、さらに死の恐怖から乗り越えられる「術」を捜しつづけています。そして、わずかなヒントかもしれませんが、少しづつそのわずかなヒントが見つかってきています。
<21世紀における「医は仁術」>
私の願いは、勿論、がんを克服して、がんが治ってしまうことです。勿論、そうですし、その為に私たちは日夜努力しています。
しかし、人はいつかは死ななければなりません。その死が近づいた時に、どのようにしてか、安寧な心で過ごすことが出来ないかということです。
医は仁術と言われます。仁とは「思いやり」です。20世紀はがんを隠し、死を隠すことで仁を発揮しました。21世紀は真実を伝え、死が近いことを告げ、そして、この仁を、思いやりをどう発揮するのか、われわれ医療者の大きな課題であると思います。
最後に 宣伝になってしまいますが、たくさんの患者さんのエピソード、そしていくつかの死の恐怖を乗り越えるヒントを、講談社現代新書「がんを生きる」(756円)に書きました。
お読みいただければ幸いです。
私は、さらに死の恐怖から乗り越えられる「術」を捜しつづけています。
短い命の宣告で、奈落に落とされた患者さんを、応援しています。
応援しています。
しかし、人はいつかは死ななければなりません。その死が近づいた時に、どのようにしてか、安寧な心で過ごすことが出来ないかということです。
医は仁術と言われます。仁とは「思いやり」です。20世紀はがんを隠し、死を隠すことで仁を発揮しました。21世紀は真実を伝え、死が近いことを告げ、そして、この仁を、思いやりをどう発揮するのか、われわれ医療者の大きな課題であると思います。
最後に 宣伝になってしまいますが、たくさんの患者さんのエピソード、そしていくつかの死の恐怖を乗り越えるヒントを、講談社現代新書「がんを生きる」(756円)に書きました。
お読みいただければ幸いです。
私は、さらに死の恐怖から乗り越えられる「術」を捜しつづけています。
短い命の宣告で、奈落に落とされた患者さんを、応援しています。
応援しています。

略歴
佐々木 常雄(ささき つねお)
昭和45年弘前大学医学部卒業後、青森県立中央病院第3内科医員を経て昭和47年国立がんセンター内科レジデント。都立駒込病院化学療法科、同部長を経て 平成13年同副院長、平成20年同院長、現職。
学会役員・評議員等:日本癌治療学会・監事・評議員、日本臨床腫瘍学会評議員、日本がん治療認定医機構理事、東京癌化学療法研究会理事、癌と化学療法誌編集委員長、全国がんセンター協議会理事。
著書:癌化学療法ベスト・プラクティス 編集 照林社(2008年)、「がんを生きる」 講談社現代新書(2009年)、「がん診療パーフェクト」編集 羊土社(2010年) 他
昭和45年弘前大学医学部卒業後、青森県立中央病院第3内科医員を経て昭和47年国立がんセンター内科レジデント。都立駒込病院化学療法科、同部長を経て 平成13年同副院長、平成20年同院長、現職。
学会役員・評議員等:日本癌治療学会・監事・評議員、日本臨床腫瘍学会評議員、日本がん治療認定医機構理事、東京癌化学療法研究会理事、癌と化学療法誌編集委員長、全国がんセンター協議会理事。
著書:癌化学療法ベスト・プラクティス 編集 照林社(2008年)、「がんを生きる」 講談社現代新書(2009年)、「がん診療パーフェクト」編集 羊土社(2010年) 他