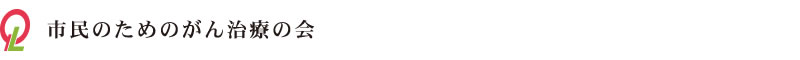『原発事故の健康被害-現況を憂う』
「市民のためのがん治療の会」代表協力医
(独立行政法人国立病院機構) 北海道がんセンター
院長(放射線治療科) 西尾正道
(独立行政法人国立病院機構) 北海道がんセンター
院長(放射線治療科) 西尾正道
作業員に対する被ばく対応の問題
この2カ月余りの経過を報道で知る限り、住民や原発事故の収拾に携わる作業員の健康被害について極めて問題がある。事故発生後、早々と作業員の緊急時被ばく線量の年間限度値を100mSvから250mSvに上げたが、この姿勢はご都合主義そのものである。250mSvは遺伝的影響は別として、臨床症状は呈しないと言われる線量である。「ただちに健康被害は出ない」上限値である。しかし作業員の健康被害を考慮すれば、やはり法律を順守した対応が求められる。
また通常は13,000cpm(4000Bq/m2)以上を除染対象としていたが、入浴もできない環境下で、いつのまにか除染基準を100,000cpmとした。また被ばく線量のチェックでは、ポケツト線量計も持たせず、またアラームが鳴らない故障した線量計を渡すなど、下請・孫請け作業員の無知に付け込んだ信じられない東電の対応である。さらに作業中のみ線量計は持たされても、それ以外は個人線量計も持たせていないのは論外である。寝食している場所も決して通常の空間線量率の場所ではないのである。また放射性物質が飛散した環境下では最も重要な内部被ばくもホールボディカウンタで把握し加算すべきである。これでもガンマー線の把握だけなのである。
原発周辺の作業地域は中性子線もあるであろうし、プルトニウムからのアルファ線もストロンチウムからのベータ線も出ているであろう。線質の違いにより測定する測定器や測定方法が異なるため、煩雑で手間暇がかかるとしても内部被ばくの把握は最も重要なことである。インターネット上の作業員の証言では通常よりは2桁内部被ばく線量も多くなっているという。このような対応の改善が無ければ、まさに「静かなる殺人」行為が行われていると言わざるを得ない。
5月24日には1~3号機の全てで原発がメルトダウン(炉心溶融)の状態であることが発表され、事態はより深刻となっている。今後は膨大なマンパワーで被ばくを分散して収拾するしかない。3号機はMOX燃料であり、ガンマー線の20倍も強い毒性を持つα線を出す半減期2万4000年のプルトニウム-239も出ている作業環境である。そのためには多くの作業員を雇用して、原発建屋や配管などの詳細な設計図や作業工程を熟知させて作業に当たる必要がある。しかしその準備の気配もない。現在は5千人前後の人達が原発の収拾に携わっているらしいが、作業員の線量限度を守るとすれば、百倍、千倍の作業員が必要となる可能性がある。
作業員に対して事前に造血幹細胞採取を行い、骨髄死の可能性を極力避ける工夫も提案されたが、無視されたままである。このままでは、いつもながらの死亡者が出なければ問題としない墓石行政、墓石対応となる。
また通常は13,000cpm(4000Bq/m2)以上を除染対象としていたが、入浴もできない環境下で、いつのまにか除染基準を100,000cpmとした。また被ばく線量のチェックでは、ポケツト線量計も持たせず、またアラームが鳴らない故障した線量計を渡すなど、下請・孫請け作業員の無知に付け込んだ信じられない東電の対応である。さらに作業中のみ線量計は持たされても、それ以外は個人線量計も持たせていないのは論外である。寝食している場所も決して通常の空間線量率の場所ではないのである。また放射性物質が飛散した環境下では最も重要な内部被ばくもホールボディカウンタで把握し加算すべきである。これでもガンマー線の把握だけなのである。
原発周辺の作業地域は中性子線もあるであろうし、プルトニウムからのアルファ線もストロンチウムからのベータ線も出ているであろう。線質の違いにより測定する測定器や測定方法が異なるため、煩雑で手間暇がかかるとしても内部被ばくの把握は最も重要なことである。インターネット上の作業員の証言では通常よりは2桁内部被ばく線量も多くなっているという。このような対応の改善が無ければ、まさに「静かなる殺人」行為が行われていると言わざるを得ない。
5月24日には1~3号機の全てで原発がメルトダウン(炉心溶融)の状態であることが発表され、事態はより深刻となっている。今後は膨大なマンパワーで被ばくを分散して収拾するしかない。3号機はMOX燃料であり、ガンマー線の20倍も強い毒性を持つα線を出す半減期2万4000年のプルトニウム-239も出ている作業環境である。そのためには多くの作業員を雇用して、原発建屋や配管などの詳細な設計図や作業工程を熟知させて作業に当たる必要がある。しかしその準備の気配もない。現在は5千人前後の人達が原発の収拾に携わっているらしいが、作業員の線量限度を守るとすれば、百倍、千倍の作業員が必要となる可能性がある。
作業員に対して事前に造血幹細胞採取を行い、骨髄死の可能性を極力避ける工夫も提案されたが、無視されたままである。このままでは、いつもながらの死亡者が出なければ問題としない墓石行政、墓石対応となる。
地域住民に対する対応の問題
地震と津波の翌日に水素爆発で飛散した放射線物質は風向きや地形の違いにより、距離だけでは予測できない形で周辺地域を汚染した。多額の研究費を費やしたとされるSPEEDIの情報は封印され、活用されることなく3月12日以降の数日間で大量の被ばく者を出した。SPEEDIの情報は23日に公開されたが、公開できないほどの高濃度の放射線物質が飛散したことによりパニックを恐れて公開しなかったとしか考えられない。
郡山市の医院では、未使用のX線フィルムが感光したという話も聞いている。また静岡県の茶葉まで基準値以上の汚染が報告されているとしたら、半減期8日のヨウ素からの放射能が減ってから23日に公開したものと推測できる。
管首相の不信任政局のさなか、原口前総務大臣はモニタリングポストの数値が公表値より3桁多かったと発言しているが、事実とすれば国家的な犯罪である。情報が隠蔽されれば、政府外の有識者からの適切な助言は期待できず、対応はミスリードされる。「がんばろう、日本 !」と百万回叫ぶより、真実を一度話すことが重要なのである。3月23日以前の国民が最も被ばくした12日間のデータを公開すべきである。全く不誠実な対応であるが、その後も不十分な情報公開の状態が続いている。
そして現在も炉心溶融した3基の原子炉から少なくなったとはいえ放射性物質の飛散は続いているが、収束の兆しは全く見えてこない。
日本の法律上では一般公衆の線量限度は1mSv/年であるが、政府は国際放射線防護委員会(ICRP)の基準をもとに警戒区域や計画的避難区域を設け、校庭の活動制限の基準を3.8μSv/hとし、住民には屋外で8時間、屋内で16時間の生活パターンを考えて、「年間20mSv」とした。文科省が基準としたICRP 2007年勧告では、「緊急時被ばく状況」では20 mSv~100 mSv/年を、またICRP 2008勧告では、「緊急時被ばく状況」後の復興途上の「現存被ばく状況」では1 mSv-20 mSv(できるだけ低く)に設定することを勧告している。
政府は移住を回避するために、復興期の最高値20mSvを採用したのである。しかし原発事故の収拾の目途が立っていない状況で住民に20mSv/年を強いるのは人命軽視の対応である。この線量基準は年齢も考慮せずに、放射線の影響を受けやすい成長期の小児や妊婦にまで一律に「年間20mSv」を当てはめるのは危険であり、私も高いと考えている。妊娠判明から出産までの期間の妊婦の限度値2mSvの10倍であり、見識のある数値とは言えない。
しかし私は、「年間20mSv」という数値以上に内部被ばくが全く計算されていないことが最大の問題であると考えている。現在の国際的な放射線の健康被害は、「しきい値なしの直線モデル」【 (LNT(linear non-threshold)仮説 】 で考えるべきとされている。これは広島・長崎の原爆被爆者のデータをもとに、直線的に低線量でも健康被害があるとするものである。現在も使われているICRP 1990年勧告による発がんリスクで考えれば、図の如くとなる。
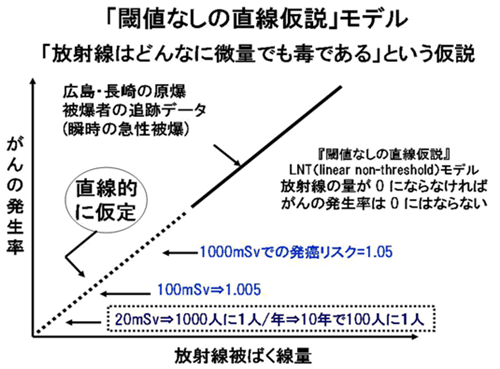
近年の報告では、広島・長崎の原爆被爆者に関するPrestonらの包括的な報告では低線量レベル(100mSv以下)でもがんが発生していると報告され、白血病を含めて全てのがんの放射線起因性は認めざるを得ないとし、被爆者の認定基準の改訂にも言及している。また、15カ国の原子力施設労働者40万人以上(個人の被曝累積線量の平均は19.4mSv)の追跡調査でも、がん死した人の1~2%は放射線が原因と報告されている。
こうした報告もあり、米国科学アカデミーのBEIR-Ⅶ(Biological Effects of Ionizing Radiation-Ⅶ、電離放射線の生物学的影響に関する第7報告, 2008)では、「しきい値なしの直線モデル」は妥当であり、発がんリスクについて「放射線に安全な量はない」と結論付けている。
さらに、欧州の環境派グループが1997年に設立したECRR(欧州放射線リスク委員会)は、国際的権威(ICRP、UNSCEAR、BEIR)が採用している現行の内部被ばくを考慮しないリスクモデルを再検討しようとするグループであるが、ECRRの手法で予測した福島原発事故による今後50年間の過剰がん患者数を41万7千人と予測している。しかし計算の根拠とした幾つかの仮定や条件が理解できない点も混在しており、予測値は誇張気味である。ちなみにICRPの方法では50年間で余分ながん発症は6,158人と予測されている。さてこの予測者数の大きな違いをどう解釈すべきなのであろうか。
郡山市の医院では、未使用のX線フィルムが感光したという話も聞いている。また静岡県の茶葉まで基準値以上の汚染が報告されているとしたら、半減期8日のヨウ素からの放射能が減ってから23日に公開したものと推測できる。
管首相の不信任政局のさなか、原口前総務大臣はモニタリングポストの数値が公表値より3桁多かったと発言しているが、事実とすれば国家的な犯罪である。情報が隠蔽されれば、政府外の有識者からの適切な助言は期待できず、対応はミスリードされる。「がんばろう、日本 !」と百万回叫ぶより、真実を一度話すことが重要なのである。3月23日以前の国民が最も被ばくした12日間のデータを公開すべきである。全く不誠実な対応であるが、その後も不十分な情報公開の状態が続いている。
そして現在も炉心溶融した3基の原子炉から少なくなったとはいえ放射性物質の飛散は続いているが、収束の兆しは全く見えてこない。
日本の法律上では一般公衆の線量限度は1mSv/年であるが、政府は国際放射線防護委員会(ICRP)の基準をもとに警戒区域や計画的避難区域を設け、校庭の活動制限の基準を3.8μSv/hとし、住民には屋外で8時間、屋内で16時間の生活パターンを考えて、「年間20mSv」とした。文科省が基準としたICRP 2007年勧告では、「緊急時被ばく状況」では20 mSv~100 mSv/年を、またICRP 2008勧告では、「緊急時被ばく状況」後の復興途上の「現存被ばく状況」では1 mSv-20 mSv(できるだけ低く)に設定することを勧告している。
政府は移住を回避するために、復興期の最高値20mSvを採用したのである。しかし原発事故の収拾の目途が立っていない状況で住民に20mSv/年を強いるのは人命軽視の対応である。この線量基準は年齢も考慮せずに、放射線の影響を受けやすい成長期の小児や妊婦にまで一律に「年間20mSv」を当てはめるのは危険であり、私も高いと考えている。妊娠判明から出産までの期間の妊婦の限度値2mSvの10倍であり、見識のある数値とは言えない。
しかし私は、「年間20mSv」という数値以上に内部被ばくが全く計算されていないことが最大の問題であると考えている。現在の国際的な放射線の健康被害は、「しきい値なしの直線モデル」【 (LNT(linear non-threshold)仮説 】 で考えるべきとされている。これは広島・長崎の原爆被爆者のデータをもとに、直線的に低線量でも健康被害があるとするものである。現在も使われているICRP 1990年勧告による発がんリスクで考えれば、図の如くとなる。
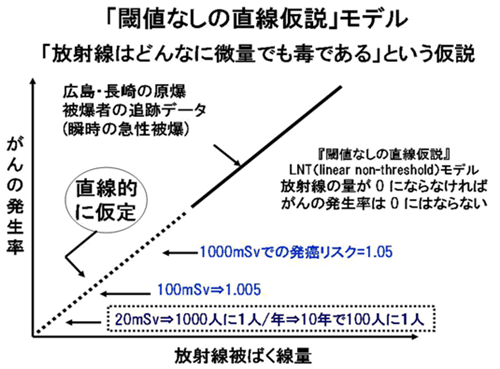
近年の報告では、広島・長崎の原爆被爆者に関するPrestonらの包括的な報告では低線量レベル(100mSv以下)でもがんが発生していると報告され、白血病を含めて全てのがんの放射線起因性は認めざるを得ないとし、被爆者の認定基準の改訂にも言及している。また、15カ国の原子力施設労働者40万人以上(個人の被曝累積線量の平均は19.4mSv)の追跡調査でも、がん死した人の1~2%は放射線が原因と報告されている。
こうした報告もあり、米国科学アカデミーのBEIR-Ⅶ(Biological Effects of Ionizing Radiation-Ⅶ、電離放射線の生物学的影響に関する第7報告, 2008)では、「しきい値なしの直線モデル」は妥当であり、発がんリスクについて「放射線に安全な量はない」と結論付けている。
さらに、欧州の環境派グループが1997年に設立したECRR(欧州放射線リスク委員会)は、国際的権威(ICRP、UNSCEAR、BEIR)が採用している現行の内部被ばくを考慮しないリスクモデルを再検討しようとするグループであるが、ECRRの手法で予測した福島原発事故による今後50年間の過剰がん患者数を41万7千人と予測している。しかし計算の根拠とした幾つかの仮定や条件が理解できない点も混在しており、予測値は誇張気味である。ちなみにICRPの方法では50年間で余分ながん発症は6,158人と予測されている。さてこの予測者数の大きな違いをどう解釈すべきなのであろうか。
内部被ばくの問題
白血病や悪性リンパ腫などの血液がんにおいて、標準治療として全身照射が行われているが、その線量は12Gy/6分割/3日である。しかしこの線量で死亡することはない。全身被ばくの急性放射線障害は原爆のデータから、致死線量7Sv、半数致死線量4Sv、死亡率ゼロの『しきい値』線量1Svの線量死亡率曲線を導き出し、米国防総省・原子力委員会の公的見解としている。しかしがん治療で行われる全身照射12Gy(Sv)では死亡しない。また医療用注射器の滅菌には20,000Gy(=Sv)、ジャガイモの発芽防止には150Gy(=Sv)照射されている。しかしこうした被ばくは一過性に放射線が照射されるだけで、照射されたものに放射線は残留していない。このため、医療でのX線検査後に除染などはしない。
しかし放射性物質からの被ばくでは、人体に取り込まれた放射性物質から微量であっても照射され続けるという極めて長期的・連続的に放射線を浴び続けることとなり、人体への影響はより強いものとなる。したがってパニックを避けるためにCT撮影では6.9mSvであるなどと比較して語るのは厳密に言えば適切な比較ではない。また画像診断や放射線治療では患者に利益をもたらすものであり、被ばくするのは撮影部位や治療部位だけの局所被ばくであり、当該部位以外の被ばくは極微量な散乱線である。内部被ばくを伴う放射性物質からの全身被ばくとは全く異なるものであり、線量を比較すること自体が間違いなのである。一過性に放射線を浴びる外部被ばくと、放射線物質が体表面に付着したり、呼吸や食物から吸収されて体内で放射線を出し続ける内部被ばくの影響を投与時の線量が同じでも人体への影響も同等と考えるべきではないのである。現在の20mSv問題は、より人体影響の強い内部被ばくを考慮しないで論じられており、飛散した放射性物質の呼吸系への取り込みや、地産地消を原則とした食物による内部被ばくは全く考慮されていないのである。通常の場合は、内部被ばくは全被ばく量の1~2%と言われているが、現在の被ばく環境は全く別であり、内部被ばくのウエイトは非常に高く、人体への影響は数倍あると考えるべきである。早急にホールボディカウンタによる内部被ばく線量の把握を行い、空間線量率で予測される外部被ばく線量に加算して総被ばく線量を把握すべきである。全員の測定は無理であるから、ランダムに抽出して平均的な内部被ばく線量の把握が必要である。
さらに飲食物に関する規制値(暫定値)の年間線量限度を放射性ヨウ素では50mSv/年、放射性セシウムでは 5mSv/年に緩和し、しかも従来の出荷時の測定値ではなく、食する状態での規制値とした。呆れたご都合主義の後出しジャンケンである。これではますます内部被ばくは増加する。ちなみにほうれん草の暫定規制値は放射性ヨウ素では2000Bq/kg、放射性セシウムでは500Bq/kgとなったが、小出裕章氏によると、よく水洗いすれば2割削減され、茹でて4割削減され、口に入る時は出荷時の約4割になるという。調理により人体への取り込みは少なくなるが、汚染水が下水に流れていくことにより、環境汚染がすすむことは避けられない。生体に取り込まれた放射線は排泄もされるため生物学的半減期や実効半減期があるが、元素の崩壊により発生した放射線は物理的半減期の時間のルールでしか減らないのである。
現在、膨大な量の汚染水を貯蔵しているが、これも限界があり、長期的には地下や川や海へ流れることになるため、日本人は土壌汚染と海洋汚染により、内部被ばく線量の増加を覚悟する必要がある。
しかし放射性物質からの被ばくでは、人体に取り込まれた放射性物質から微量であっても照射され続けるという極めて長期的・連続的に放射線を浴び続けることとなり、人体への影響はより強いものとなる。したがってパニックを避けるためにCT撮影では6.9mSvであるなどと比較して語るのは厳密に言えば適切な比較ではない。また画像診断や放射線治療では患者に利益をもたらすものであり、被ばくするのは撮影部位や治療部位だけの局所被ばくであり、当該部位以外の被ばくは極微量な散乱線である。内部被ばくを伴う放射性物質からの全身被ばくとは全く異なるものであり、線量を比較すること自体が間違いなのである。一過性に放射線を浴びる外部被ばくと、放射線物質が体表面に付着したり、呼吸や食物から吸収されて体内で放射線を出し続ける内部被ばくの影響を投与時の線量が同じでも人体への影響も同等と考えるべきではないのである。現在の20mSv問題は、より人体影響の強い内部被ばくを考慮しないで論じられており、飛散した放射性物質の呼吸系への取り込みや、地産地消を原則とした食物による内部被ばくは全く考慮されていないのである。通常の場合は、内部被ばくは全被ばく量の1~2%と言われているが、現在の被ばく環境は全く別であり、内部被ばくのウエイトは非常に高く、人体への影響は数倍あると考えるべきである。早急にホールボディカウンタによる内部被ばく線量の把握を行い、空間線量率で予測される外部被ばく線量に加算して総被ばく線量を把握すべきである。全員の測定は無理であるから、ランダムに抽出して平均的な内部被ばく線量の把握が必要である。
さらに飲食物に関する規制値(暫定値)の年間線量限度を放射性ヨウ素では50mSv/年、放射性セシウムでは 5mSv/年に緩和し、しかも従来の出荷時の測定値ではなく、食する状態での規制値とした。呆れたご都合主義の後出しジャンケンである。これではますます内部被ばくは増加する。ちなみにほうれん草の暫定規制値は放射性ヨウ素では2000Bq/kg、放射性セシウムでは500Bq/kgとなったが、小出裕章氏によると、よく水洗いすれば2割削減され、茹でて4割削減され、口に入る時は出荷時の約4割になるという。調理により人体への取り込みは少なくなるが、汚染水が下水に流れていくことにより、環境汚染がすすむことは避けられない。生体に取り込まれた放射線は排泄もされるため生物学的半減期や実効半減期があるが、元素の崩壊により発生した放射線は物理的半減期の時間のルールでしか減らないのである。
現在、膨大な量の汚染水を貯蔵しているが、これも限界があり、長期的には地下や川や海へ流れることになるため、日本人は土壌汚染と海洋汚染により、内部被ばく線量の増加を覚悟する必要がある。
今後の対応について
現在、医療従事者の約44万人が個人線量計(ガラスバッジ)を使用しているというが、千代田テクノル社の24万4千人の平成21年度の個人線量当量の集計報告では、一人平均年間被ばく実効線量は0.21mSvである。そして検出限界未満(50μSv)の人は全体の81.5%であり、年間1mSv以下の人は94.5%である。ガラスバッジの生産に数カ月要するとしたら、1mSv以下の23万人分の線量計を一時的に借用して、原発周辺の子供や妊婦や妊娠可能な若い女性に配布すべきである。移住させずにこのまま生活を継続させるのであれば、塵状・ガス状の放射性物質からの被ばく線量は気象条件・風向き・地形条件だけでなく、個々人の生活パターンにより大きく異なるため、個人線量計を持たせて実側による健康管理が必要である。またランダム抽出によりできるだけ多くの人の内部被ばく線量の測定も行い、地域住民の集団予測線量も把握すべきである。
また環境モニタリング値を住民がリアルタイムで知ることができるような掲示を行い、自分で被ばく量の軽減に努力できる情報提供が必要である。また測定点はフォールアウトし地面を汚染しているセシウムからの放射線を考慮して地面直上、地上から30~50cm(子供)用、1m(大人用)の高さで統一し、生殖器レベルでの空間線量率を把握すべきである。
土壌汚染に関しては、学校の校庭の土壤の入れ替え作業も一つの対策だが、24時間の生活の中で被ばく低減の効果には限界がある。
結論として私の本音は移住させるべきと考えている。原発事故の収拾に全く目途が無い状態では長期化することは必至であり、避難所暮らしも限界がある。このままでは年金受給者と生活保護者も増え、汚染された田畑や草原では農産物も作れず畜産業も成り立たない。放射線の影響を受けやすい小児や子供だけが疎開すればよいという事ではない。住民の経済活動そのものが成り立たない可能性が高いのである。
またストロンチウムなどの種々の核種の詳細な情報は報道されていないが、ストロンチウムは骨に沈着し、成長期の子供の骨の成長障害の原因ともなる。
メンタルケアの問題も、毎日悪夢のような事態を思い出す土地で放射能の不安を抱えながら生活するよりは、新天地で生活するほうが精神衛生は良い。移住を回避するという前提での理由づけは幾らでもできるが、健康被害を回避することを最優先にすべきである。
政府は土地・家屋を買い上げ、まとまった補償金・支援金を支給して新天地での人生を支援すべきである。また、70~80歳を過ぎた老夫婦が多少の被ばくを受けても「終の棲家」として原発周辺で住むのも認めるべきである。老人の転居はむしろ身体的にも精神的にも健康を害するからである。お上のすべきことは正確な情報を公開し、住民に選択権を与え、支援することである。
今までの政府・東電の対応を見れば、馬鹿かお人好し以外の国民は「絵に描いた餅の行程表」など誰も信用していない。長い眼で見れば健康で労働できる人を確保することが、国としての持ち出しは少なくなるのである。
また環境モニタリング値を住民がリアルタイムで知ることができるような掲示を行い、自分で被ばく量の軽減に努力できる情報提供が必要である。また測定点はフォールアウトし地面を汚染しているセシウムからの放射線を考慮して地面直上、地上から30~50cm(子供)用、1m(大人用)の高さで統一し、生殖器レベルでの空間線量率を把握すべきである。
土壌汚染に関しては、学校の校庭の土壤の入れ替え作業も一つの対策だが、24時間の生活の中で被ばく低減の効果には限界がある。
結論として私の本音は移住させるべきと考えている。原発事故の収拾に全く目途が無い状態では長期化することは必至であり、避難所暮らしも限界がある。このままでは年金受給者と生活保護者も増え、汚染された田畑や草原では農産物も作れず畜産業も成り立たない。放射線の影響を受けやすい小児や子供だけが疎開すればよいという事ではない。住民の経済活動そのものが成り立たない可能性が高いのである。
またストロンチウムなどの種々の核種の詳細な情報は報道されていないが、ストロンチウムは骨に沈着し、成長期の子供の骨の成長障害の原因ともなる。
メンタルケアの問題も、毎日悪夢のような事態を思い出す土地で放射能の不安を抱えながら生活するよりは、新天地で生活するほうが精神衛生は良い。移住を回避するという前提での理由づけは幾らでもできるが、健康被害を回避することを最優先にすべきである。
政府は土地・家屋を買い上げ、まとまった補償金・支援金を支給して新天地での人生を支援すべきである。また、70~80歳を過ぎた老夫婦が多少の被ばくを受けても「終の棲家」として原発周辺で住むのも認めるべきである。老人の転居はむしろ身体的にも精神的にも健康を害するからである。お上のすべきことは正確な情報を公開し、住民に選択権を与え、支援することである。
今までの政府・東電の対応を見れば、馬鹿かお人好し以外の国民は「絵に描いた餅の行程表」など誰も信用していない。長い眼で見れば健康で労働できる人を確保することが、国としての持ち出しは少なくなるのである。
おわりに
原子力利用による電力確保は国策民営として勧められ、地域住民には多額の原発交付金を与え懐柔してきた。こうした、札束で人心を動かす手法で、54基の原発を持つ原発大国となったが、原子力行政は根本から見直しを迫られている。原子力発電の廃炉後の管理や使用済み燃料の保管や事故が起こった場合の補償まで視野に入れた場合、コスト的にも原発が優位性を持つものではないことが明らかになった。しかしIT社会や電気自動車の普及など今後の電力需要は増すばかりであり、節電だけでは対応できないことも事実である。脱原発の方向でソフトランディングする施策を根本的に議論すべきであろう。米国も1979年のスリーマイル島事故以来、新たな原発は稼働させていないのである。
2011年6月5日 記
西尾 正道(にしお まさみち)
独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター院長。函館市出身。1974年札幌医科大学卒業後、国立札幌病院・北海道地方がんセンター放射線科勤務。1988年同科医長。2004年4月、機構改革により国立病院機構北海道がんセンターと改名後も同院に勤務し現在に至る。がんの放射線治療を通じて日本のがん医療の問題点を指摘し、改善するための医療を推進。
著書に『がん医療と放射線治療』2000年4月刊 (エムイー振興協会)、『がんの放射線治療』2000年11月刊(日本評論社)、『放射線治療医の本音-がん患者2万人と向き合って-』2002年6月刊( NHK出版)、『今、本当に受けたいがん治療』2009年5月刊 (エムイー振興協会)の他に放射線治療領域の専門著書・論文多数
独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター院長。函館市出身。1974年札幌医科大学卒業後、国立札幌病院・北海道地方がんセンター放射線科勤務。1988年同科医長。2004年4月、機構改革により国立病院機構北海道がんセンターと改名後も同院に勤務し現在に至る。がんの放射線治療を通じて日本のがん医療の問題点を指摘し、改善するための医療を推進。
著書に『がん医療と放射線治療』2000年4月刊 (エムイー振興協会)、『がんの放射線治療』2000年11月刊(日本評論社)、『放射線治療医の本音-がん患者2万人と向き合って-』2002年6月刊( NHK出版)、『今、本当に受けたいがん治療』2009年5月刊 (エムイー振興協会)の他に放射線治療領域の専門著書・論文多数