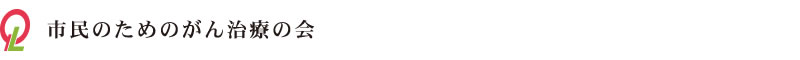『より効くキイトルーダ対策か やっと薬価引き下げ、の茶番
オプジーボの光と影⑤』
実は免疫チェックポイント阻害剤という画期的な薬についての議論も、同じような構造ではないか。
今回の騒動を通じて、薬事業界も利益確保を確実にし、学会や行政側にも利益があるような解決が行われようとしていることが明らかになってきた。消費者=患者のためになるような検討が行われたのだろうか、その形跡は寡聞にして知らない。これではPatient firstどころか、業界、官界、学会firstではないか。
なかなか消費者には分かりにくいが、オプジーボについて連続してその核心を解説して下さっておりますロハス・メディカル編集発行人 川口恭先生に引き続き転載をご許可いただきました、ご厚意に深く感謝いたします。
理不尽なまでに高いオプジーボ(ニボルマブ)の薬価は、どうやら2018年4月の定期薬価改定を待たず2017年中にも引き下げられるようです。しかし同時に、公益を考えているとは思えない言動が業界で相次ぎ、とんだ茶番と言わざるを得ません。
これまでなら治療法のなかった末期がん患者さんたちに希望の火を灯しているオプジーボは、腎細胞がんへの適応拡大も承認されることになりました。対象者やご家族にとって実に嬉しい知らせだろうと思います。そのように希望の火が広がっていくのは素晴らしいことです。
一方で、その薬価がとてつもなく高く、健康保険財政と蔭に控える国家財政を圧迫、社会問題化しています。問題の薬価が、厚生労働省と薬価について審議する中央社会保険医療協議会(中医協)の怠慢そして薬価算定制度の不備によって生じているものであり、現行ルール通りの用量変更による再算定を行った場合の2・25倍、ルール変更に踏み込み対象患者数拡大まで反映して算定し直すとした場合の10倍以上になってしまっていることは、この連載の初回に指摘しました。
現行の薬価改定は、診療報酬改定と同時に2年に1度行われることになっていて、つまりオプジーボの薬価はこのまま何もしないと2018年4月まで引き下げられないことになります。さすがに中医協でも4月13日の総会で、発言力の大きな中川俊男委員(日本医師会副会長)が「薬価収載された医薬品の効能・効果が大幅に拡大された場合に、(中略)薬価がそのままというのは誰が考えてもおかしい。(中略)対象が拡大された時点、効能・効果が拡大された時点で薬価を見直すという仕組みにはできないのでしょうか」と問題提起、厚労省の担当者も「今後そういったルールをしっかり議論していく必要がございます」と答えるやりとりが行われ、対応を探るようになりました。
厚労省は3カ月半後、7月27日の中医協総会で、オプジーボに関して「特例的な対応」の検討を提案、翌8月に開かれた同薬価専門部会では10月に「緊急的な対応」の案を示すと明らかにしました。これにより、オプジーボの薬価が2017年中に引き下げられることは、ほぼ間違いないと見られます。加えて厚労省は、オプジーボを含む「新規作用機序医薬品」の「最適使用推進ガイドライン」なるものを策定し、使える患者や医療機関、医師の要件を定める方針も明らかにしています。
うごめく欲張り村
厚労省はさらに、今回判明した不備を修正すべく、「効能追加などで大幅に市場規模が拡大した場合」「薬価収載当初から市場規模が極めて大きい場合」に対応できる抜本的な制度改革の検討も提案しました。
この一連の動きを見れば、ようやく制度の不備が修正され、一般社会から見て受け容れやすい形に近づくのだな、と普通の人は思うところでしょう。
しかし残念ながら、そうならない可能性が高そうです。
7月の中医協総会で、元々は制度見直しを強く主張していたはずの中川委員は、煮え切らない態度に終始しました。
これについて、業界誌『医薬経済』の2016年8月15日号は、
――この真意について、中川氏は中医協後、本誌などに「17年度に期中改定を行わずに、その分は『貯金』しておいて、18年度にまとめて薬価を引き下げることも検討に値するのではないか、という意味だ」と語っている。オプジーボを含む薬価引き下げ財源を、あくまで診療報酬本体に充当することを前提にすべきとのスタンスを示したことになる。
と書いています。
多くの方は、何を書いてあるのか分からないと思います。分からなくて当然です。一般人からすると信じられない業界の常識が前提になっているからです。
その前提とは、これまで定例の薬価改定(引き下げ)でお金が浮くと、そのお金は原則として診療報酬改定(引き上げ)の原資になっていた、ということです。よって中川委員の発言の意図は、診療報酬改定がない年にお金を浮かしても業界内では使えないので、制度を抜本的に改革したら業界が損をする、ということになります。いったん医療の財布に入った以上、それは業界で使って当然だ、という意識です。
記者相手に解説してみせるくらいですから、それほど変なことをしているという意識はないのでしょう。ただ、普通の感覚では、元を辿れば保険料や公費なのだから社会に返すのが当然、と思うはずです。もしオプジーボ騒動に良かった点があるとするなら、業界のこの狂った常識が白日の下に晒されたことなのかもしれません。
ちゃっかり利権拡大
というわけで、社会が強く要求しない限り制度の抜本改革は骨抜きになり、オプジーボの特例改定と「新規作用機序医薬品」に関するガイドラインの整備だけが進みそうです。
この点について、少しでも前に進むのだから良しとすべきじゃないか、と思っている方がいるなら、とんでもない勘違いだと申し上げておきます。厚労省は、自分たちの不手際を反省するどころか、ドサクサ紛れに利権拡大を図っているとしか考えられません。
先に、ガイドラインの方の問題点を指摘してしまいます。
使うべき患者の基準を定めるのは当たり前の話ですが、それが科学的根拠や医学的妥当性に基づくものでない場合は医療不信のタネになるということを、本連載の2回目で指摘しました。そして科学的根拠や医学的妥当性は、既に薬事承認審査の段階で検討され、それに基づいて適用が定められているわけです。その適用を保険償還の段階でさらに絞り込もうとするなら、科学的根拠や医学的妥当性ではない物差しを持ち込む必要があり、これまで薬事審査と保険がほぼ直結運用されてきた歴史を踏まえると、そんなに簡単な話ではありません。よって、今回の検討の主眼は、新規作用機序薬剤(要するに高額な薬剤)を処方できる医療機関や医師の要件を定めることにあると言えます。
この要件とは一体どういうものになるでしょうか。要件が定められると一体どういうことが起きるでしょうか。
オプジーボの場合、メーカーである小野薬品工業が専門家と協議して定めた自主基準で、処方できる施設の要件として第一に、①日本呼吸器学会の専門医が当該診療科に在籍 ②日本臨床腫瘍学会のがん薬物療法専門医が当該診療科に在籍 ③がん診療連携拠点病院、特定機能病院、外来化学療法室を設置している施設のいずれか のどれかを満たすよう求めています。③の施設で①②が1人もいないということは考えにくいので、実態としては専門医の有無が線引きの境目になっていると分かります。
新たに定められるガイドラインも、客観性を担保しようとするなら、似たようなことにならざるを得ないでしょう。
これについて、医師の上昌広・医療ガバナンス研究所理事長は、web雑誌『Business Journal』で「大きな批判がなければ、高額薬の処方は学会の認定する専門医に限定されそうだ。(中略)厚労省、学会のいずれにも都合がいいからだ。厚労省にとっては、医療統制に使える手段が増える。学会にとっては、新たな利権の創出だ。(中略)学会は何もしなくても会員が増え、会費収入が入ってくる」と指摘します。
それが患者や社会の利益につながるのなら、利権になってしまって構わないとも言えるのですが、どう考えても不利益の方が大きそうです。
例えば、ガイドラインの基準を満たした患者が、要件を満たさない医療機関・医師を受診した時のことを考えてみてください。その医師・医療機関が、要件を満たす医師・医療機関へ直ちに紹介しないと、患者は治療の選択肢を不当に狭められることになります。患者数の少ない難病ならともかく、今回のガイドラインが必要になるのは比較的患者数の多い疾患で、その患者を直ちに他施設へ紹介する、など非現実的であることはお分かりいただけると思います。
引き下げて当然の薬価を引き下げずに、処方を絞る方で薬剤費総額を抑え込もうなどと不遜で姑息なことを考えるから、こんな机上の空論しか出てこないのです。
ライバルの登場
ここからは、今回検討されているオプジーボ薬価「特例引き下げ」に、ほとんど意味がないことを説明します。
本連載の2回目に、免疫のブレーキを外す作用の抗PD-1抗体であるオプジーボは、化学療法で免疫が傷めつけられる前の一次治療から使う方が効果を見込めるのでないかとの考え方もあること、一次治療に使う治験も行われているので、その結果次第では使われ方が変わるかもしれないことを紹介しました。
その注目の臨床試験結果は8月に発表され、非小細胞肺がんの薬物一次治療に使った場合の効果が既存の化学療法を上回れなかった(コラム参照)ため、業界に衝撃が走りました。
衝撃が走ったのは、抗PD-1抗体は薬物2次治療として使うという決着になった、からではありません。市場の勢力図が大きく塗り替わるかもしれないから、です。
本連載の3回目に紹介したように、抗PD-1抗体として、ペンブロリズマブ(商品名・キイトルーダ)というものもあり、既に悪性黒色腫と非小細胞肺がんで承認申請済みで、年内にも承認されると見られています。
そのキイトルーダでは6月に、非小細胞肺がんの一次治療で化学療法を上回る結果を出した(コラム参照)との発表があり、オプジーボでも同様の結果が出るに違いないと予測されていたのに、そうではなかったわけです。2剤で明暗が分かれ、それが業界で驚きをもって受け止められたのです。
キイトルーダの方がPD-1への親和性が高い(結合が強い)ことは、以前から知られていました。2剤の試験対象患者が完全に同じではないので決めつけるのは早計ですが、キイトルーダの方がよく効くのかもしれません。キイトルーダの米国での価格は、1人あたり年間15万ドル(約1500万円)です。今後、一次治療に用いる用法の承認申請も行われると見られます。
その薬価は?
キイトルーダが我が国でも承認され保険収載されると、当然ながら薬価が決められることになります。
現行の決まり方では、世界で最初に承認されたために原価積み上げのみで決められたオプジーボと違って、同じ作用機序の薬であるオプジーボの薬価を基準に、オプジーボより優れている点があるなら加算を行い、さらに米英独仏の平均薬価を参照して調整されるという流れになります。
分かる範囲で仮に数字を当てはめて計算してみる(コラム参照)と、1人年間約2400万円と米国での価格に比べても充分に高く、それでいてオプジーボより3割安いというメーカーからすると絶妙の金額になります。
より効くかもしれない薬が、3割安く提供されるわけですから、使える患者に関しては雪崩を打ってオプジーボからキイトルーダへと置き換えられる可能性が高いです。医師や医療機関は望まなくても、さすがに保険者が圧力をかけることでしょう。そうなれば待望の「日の丸医薬品」であるオプジーボは、一気に売上を落とすことになります。
でも、そこで「特例引き下げ」と称して、キイトルーダより少し安いくらいの薬価への調整が行われたとしたら、どうでしょう。雪崩を打つような置き換えは起きず、メーカーである小野薬品工業の利益も守られることになります。つまり今回の「特例」はメーカーに厳しい顔をして見せていますけれど、実態としては大甘なのです。
そもそもオプジーボのメーカーであるBMSと小野薬品工業は、キイトルーダのメーカーである米メルクを特許侵害で一昨年9月に訴えており、その訴えが認められれば特許のライセンス料が発生しますので、どちらの薬が売れても小野薬品工業の利益になります。キイトルーダを米国の1・6倍の値段で買わされる日本社会だけが、いい面の皮です。
ちなみに、オプジーボの薬価が用量変更による再算定ルールを厳密に適用した2・25分の1だったとしたら年間約1550万円で、米国でのキイトルーダ価格とほぼ同じということも付言しておきます。
このように考えてみると、オプジーボ騒動を本当に深刻に受け止め、公益のために対応するというなら、「特例」検討などという時間のかかることをする前に、まずは現行再算定ルールを厳密に適用して2・25分の1まで薬価を引き下げるはずです。それによって、後から承認されてくるキイトルーダの方の薬価も、米国並みで収まります。しかし、そのような動きは全くなく、小野薬品工業にとってありがたいタイミングまで引っ張ってから引き下げるという話ですから、要するに今回の厚労省の提案は騒動を煙幕に利権の拡大を図る茶番でしかないのです。
一般国民や保険者は、もっと怒るべきだと思います。
キイトルーダの薬価の試算法
外国で既に販売されている薬の算定値が外国平均価格の1.25倍を上回った場合は、以下のような計算式で導き出されます。
(1/3 × 算定値/外国平均価格 + 5/6)×外国平均価格
算定値は、先行品に比べて有用性がある場合、先行品の価格に加算が行われます。
一次治療の試験でオプジーボと明暗を分けたので、「より効く」と加算されても不思議はありませんが、高過ぎて売れないのではメーカーにとって意味がないので、ここではメーカーが加算を求めずオプジーボと同じ年間約3500万円の算定値になると仮定します。
英米独仏の平均価格がいくらになるか定かでないので、ここでは分かっている米国の価格を援用して年間1500万円としました。
それぞれの試験結果
オプジーボ
メーカーであるブリストル・マイヤーズスクイブ(BMS)の発表などによると、これまでに薬物治療を受けたことがなく腫瘍の5%以上にPD-L1が発現している非小細胞肺がんの541人を無作為に2群に分け、片方にはオプジーボを単剤使用、片方にはプラチナ製剤をベースとする化学療法を行った結果、オプジーボは、主要評価項目である無増悪生存期間(※)での優位性を示せませんでした。
キイトルーダ
メーカーである米メルクの発表などによると、これまでに薬物治療を受けたことがなく腫瘍の50%以上にPD-L1が発現している非小細胞肺がんの305人を無作為に2群に分け、片方にはキイトルーダを単剤使用、片方にはプラチナ製剤をベースとする化学療法を行った結果、無増悪生存期間および全生存期間の両方とも化学療法より優位であることが分かり、その差が明らかであるため倫理的配慮から試験は途中で中止されました。
※治療開始時点から、死亡または病状増悪が確認されるまでの時間