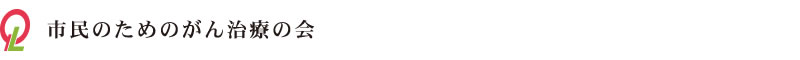『幕末の食肉事情とホルモン剤とがん』
今年のNHK大河ドラマ『西郷どん』。 明治維新からちょうど150年を記念したものです。
日本人が一般的に牛肉を食べるようになったのは明治維新以降とされていますが、実は江戸時代に唯一、牛の屠畜を認められていた藩がありました。 それが彦根藩。藩主の井伊家では毎年、太鼓の皮の張り替えに牛の皮を5枚と、牛肉を将軍家に献上していました。 そのお裾分けで牛肉が大好物だったのが、水戸藩の徳川斉昭。最後の将軍となる一橋慶喜の実父です。
ところが、井伊直弼が彦根藩主になると、敬虔な仏教徒だったこともあって、藩内での牛の屠畜を禁止してしまいます。 そうなると、毎年楽しみにしていた牛肉が水戸に届かない。 斉昭は直弼に使いを出して、「私のためだけにでも牛肉を送ってください」などと催促するのですが、直弼は頑として聞かなかった。
井伊直弼と水戸の斉昭は開国を巡って意見対立しますが、その前から牛肉を巡って不仲になった、と『水戸藩党争始末』に記されています。 水戸の脱藩藩士たちが井伊直弼を襲った桜田門外の変にも、牛肉の遺恨が反映されているのかもしれません。
また、西郷隆盛の産まれ育った薩摩藩では豚を食べていました。 彦根が牛なら、薩摩は江戸時代最大の豚肉加工基地。 江戸の藩邸でも豚を飼っていたほどです。
この豚肉が大好きだったのが一橋慶喜。 豚が大好き一橋のお殿様、という意味でついた渾名が「豚一殿」。 慶喜は薩摩に再三にわたって豚肉を督促し、若くして家老になった小松帯刀を困らせています。 いまも豚好きの慶喜を愚痴った帯刀の手紙が残っています。
こちらの遺恨は倒幕に結びつく、と言ったところでしょうか。
そうして見ると、ドラマも違った楽しみ方ができます。
あれから150年。
いま、牛肉は豪州と米国から大量に輸入されています。 平成28年度の統計を見ると、牛肉の国内生産量は32万4000トンで、豪州から27万8000トン、 次いで米国から20万7000トンが輸入され、ここ数年では豪州産が減少して、米国産の輸入量が増加している傾向にあります。 TPP(環太平洋パートナーシップ協定)を離脱したトランプ大統領ですが、 それでも日本に対して米国産牛肉の関税引き下げに言及していることからすれば、さらに売り込みに躍起になっていることがわかります。
その米国では、肉牛に成長促進ホルモン剤を投与することが一般的です。
日本の和牛ですと、生まれて食肉として出荷されるまでにおよそ30ヶ月かかりますが、米国では子牛にホルモン剤を投与することで、成長が早まり、18〜20ヶ月で出荷できます。 牡でも牝のように肉がつき、生産性の向上にもつながります。 2003年に米国でBSE(牛海綿状脳症)が発生したときに、日本は米国産牛肉の輸入を禁止するのですが、 月齢20ヶ月以下の牛にはBSEが発症しないことを理由に、米国は日本に20ヶ月以下の牛の輸入再開を求めて、これを2005年に受け入れさせています。 これもホルモン剤による効用といえます。
ホルモン剤が使われるのは肉牛に限ったことではありません。 米国では乳牛にもホルモン剤が使われます。搾乳量を増やすためです。
この乳牛用の催乳ホルモン剤を開発したのがモンサント社でした。 遺伝子組み換え作物で知られる大手企業です。 実は、このホルモン剤も遺伝子組み換えで誕生しています。 本来ならば分娩後の牛の脳下垂体で大量に分泌される天然ホルモン「ソマトトロピン」を遺伝子組み換え技術で大量生産を可能にしたことから、 「遺伝子組み換え牛ソマトトロピン」(rBST)あるいは「遺伝子組み換え牛成長ホルモン」(rBGH)と呼ばれています。
ところが、ホルモン剤を投与することで、泌乳量の多い牛にありがちな、乳房炎を発症しやすくなります。 乳房が炎症を起こし化膿するのです。 そうなると、牛の体内には白血球が増えるし、膿もいっしょに牛乳に混ざることになるのです。
そこで次に、乳房炎を治療するために抗生物質を使います。 そうすると、牛乳の中にその抗生物質が残留する可能性が出てきます。それを消費者が飲む。 これを過剰に摂取することによって、今度は抗生物質が効かない耐性菌が増えることになります。 米国では90年代の前半に、それまで下降傾向にあったはずの結核が増えていることが報告されています。 1991年にニューヨーク市で発見された結核の症例の3分の1は、医薬品に耐性を持った細菌株でした。
そして、さらに問題になるのが、がんの増加です。
人間の母乳の初乳の中にはIGF−1(「インスリン様成長因子1」もしくは「組織成長因子」)が大量に含まれ、これが赤ん坊の成長を促進させる働きをします。 このホルモンは人間の体内でも生産され、思春期にピークを迎えると年齢と共に低下していきます。
IGF−1は、あらゆる哺乳類において成長ホルモンによって肝臓でつくられます。 良い細胞も悪い細胞も、あらゆる細胞が増殖するように刺激する成長因子です。 人体での濃度が高くなると、先端巨大症(末端肥大症)や巨人症と呼ばれる病気の原因になることは知られていましたが、 近年では、乳がん、直腸がん、前立腺がんのリスクが大幅に増加する研究論文が相次いで発表されるようになりました。
ハーバード大学の研究チームによると、15万人の追跡調査の結果、IGF−1の血中濃度が高くなると、前立腺がんのリスクが4倍になったそうです。
また、50歳未満の閉経前の女性のうち、高いIGF−1濃度を示した女性は、通常の濃度の女性に比べて乳がんを発症する確率が7倍になったとする論文が専門紙に発表されています。
実はこのホルモンは、rBGHを投与された牛から搾乳された牛乳のほうが、そうでない自然の牛に比べて濃度が高くなることが報告されています。 その濃度差は75%にまで達するそうです。
そしてついには、rBGHが市販された1994年から2002年の間に、50歳以上の米国人女性の乳がん発生率が55.3%も増加したことを示す論文まで発表されます。
こうしたこともあって、いま米国の主要都市のスーパーマーケットに並ぶ牛乳のパックには 「produced without antibiotics, synthetic hormones or pesticides(抗生物質、合成ホルモン剤、殺虫剤未使用で生産)」 「from cows not treated with artificial growth hormones(人工の成長ホルモン剤を投与されていない牛から)」と記載されたものがあります。 消費者が選択できる自由があります。
ところが、日本に入る米国産の乳製品には、そんな記載も情報もありません。
肉牛の成長ホルモン剤も同様です。 EU(欧州連合)では、成長ホルモン剤の使用を一切禁止し、投与された肉の輸入も禁じています。 そのため、私が訪れた米国の食肉加工場では、欧州輸出向けにわざわざホルモン剤を使用しない牛を育てて、食肉に加工しているほどです。
日本では、国内で成長ホルモン剤の使用は認められていません。 それでも、輸入される牛肉には認められています。
さらに、豚肉。日本の豚肉の自給率は約51%です。 あとの輸入のうち、もっとも多く豚肉を日本に送っているのが、実は米国です。 米国は世界最大の豚肉輸出国なのです。
米国では、豚を出荷する直前の45〜90日の間に赤身肉を増加させる目的で「ラクトパミン」という物質を餌に混ぜて与えています。 興奮剤、成長促進剤としての作用がある、いわゆるドーピング剤です。
このラクトパミンも、やはりEUでは使用はおろか、輸入肉の残留も認めていません。 「データが十分でなくヒトの健康への影響が除外できない」というのが、その理由です。
世界一の豚肉消費量を誇る中国ですら同様です。 ロシアでも認めていません。
それが日本となると、国内での使用は禁止。 だけど、輸入肉には使用していいことになっています。
つまり、ダブルスタンダード。 米国の牛や豚には、治外法権を認めていることになります。
倒幕によって誕生した明治政府は、幕府が諸外国と結んだ不平等条約の解消に苦労しました。 すなわち、治外法権の取り消しと関税自主権の回復です。 それが、150年が経ったいまでも、米国に与えていることになります。
現状を知れば、西郷どんも豚一殿もびっくりでしょう。
ですが、そうしなければ食料自給率が39%の日本は、立ち行かなくなります。 米国に食料を依存しなければならない状況にあります。 いや、戦後の歴史の中で、米国は強かに日本の食料を支配してきた、といったほうが正確です。
例えば、遺伝子組換え作物。 2016年の日本の大豆の自給率は7%、トウモロコシにおいては1%にも満たないのが現状です。 あとは輸入に頼っているわけですが、このうち大豆の71.5%、トウモロコシの74.5%は米国からの輸入です。 その米国では同年の大豆の作付面積の94%、トウモロコシでは92%が遺伝子組み換え作物で占められているのです。 日本人はどうしても遺伝子組み換え作物に頼らざるを得ない。 その飼料で育った国産、米国産の食肉を食べることになる。 そういう構造を、戦後の経済復興と貿易関係の中で米国は着々と築いてきた。
米国からの牛肉輸入量の増加は、ここ数年の外食や家庭での牛肉消費量の伸びに結びついているとされます。 ちょっとしたブームにあります。それだけ、これからがんが増える可能性も否定できません。
それでがん保険や医療保険まで米国に牛耳られては、目も当てられなくなります。
がんを考えるとき、もう少し日本のおかれた食料事情を振り返っておきたい。 結局、食の安全も依存相手国の都合次第なのですから。
幕末の食肉事情から、現在の日本の食料事情をまとめたものが拙著です。
よろしければ参考になさってください。
第2章 豚のロビイスト
第3章 米国食肉工場の秘密
第4章 豚が空を飛ぶ
第5章 トム・ソーヤーに憧れた国家主席
第6章 ハーベストムーン
本体1400円+税
発売日2017/9/27
判型/頁4-6/258頁
作家・ジャーナリスト。1968年、長野県生まれ。 犯罪事件、社会事象などをテーマに、精力的にルポルタージュ作品を発表している。 著書に『食料植民地ニッポン』『オウム裁判傍笑記』『私が見た21の死刑判決』など。