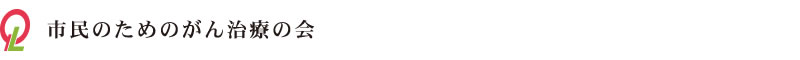『なんちゃって在宅診療を選ばないために~在宅診療の現実と課題』
院長 山中 光茂
自宅での看取りには多くの医療・医療関連スタッフを組織化した、本当に患者に寄り添う在宅診療の医師が必要である。
しかしながら在宅診療所や訪問看護ステーションの数も劇的に増えてきてはいるが、実態は本当に患者に寄り添う在宅医療は少ないようである。
人は残念ながら必ず終焉の時を迎える、がん患者も例外ではない。
そこで市長として行政トップのご経験もあり、多くのがん患者を看取り、 現在は東京・江戸川区で「しろひげ在宅診療所」(https://shirohige.clinic/)を主宰し、 その活動がテレビでも紹介されている山中 光茂先生に、ご多用の中、ご寄稿いただいた。御礼申し上げます。
2022年1月、埼玉県ふじみ野市において在宅診療の医師が担当していた患者の弔問に訪れた際に家族に猟銃で射殺されるという事件が起こった。 地域において、常に300人以上の患者を抱え、24時間365日の体制をしっかりとっており、住民や関係介護職種からの信頼も厚かったとのことである。
在宅診療の実態は、いまだに一般の方々だけではなく、メディアや自治体関係者、そして医療従事者の間ですらまだ十分な理解がされているとは言えない。 一般的なメディアなどを通じたイメージとして、病状の安定した患者を長年に渡って継続して自宅に訪問して、「おじいちゃん、おばあちゃん、今日も元気ですか?」というサポートをしている役割に思われがちである。 それは、離島や僻地または、地域での開業医による「かかりつけ医の往診」との混同があるように思われる。 もちろん、離島医療や僻地医療は地域住民にとってなくてはならないものである。 ただ、「かかりつけ医師の往診」は物理的に交通環境が不足しているなかで定期的に患者に対応したり、重症度が高くない比較的軽めの患者への緊急対応が中心となるものである。 専門外であったり、重症度が高い場合には病院への精査に回したり、救急搬送をする、という医療のやり方となる。 一方で、在宅診療においては、がんの末期や難病、重度精神障害など高度に専門的の求められる分野においても、 重症度に関わらず安易に救急搬送するのではなくて基本は自宅でその人生に寄り添って完結させようとする気概が求められる。 よくドラマなどで見られる、大きな病院につなぐまでのスーパードクターによる緊急対応とは意味合いが全く違うのである。 Dr.コトー(※1)などは、まさに在宅診療ではなくて、僻地医療における「かかりつけ医」のスーパードクター版である。 診療に来れる人は病院にきてもらい、緊急時には自分自身の医療技術でできる範囲でしっかりと命を救う、そのような役割を持っているのである。 これは基本的にはどのような病態であっても看取りまで責任をもつ在宅診療とは全く意味が異なっているのである。
2000年代前半から「地域包括ケア」という概念が国、地方自治体で広がるなかでそれを支える法制度も充実してきた。 在宅診療やその介護体制への報酬体系も潤滑に交付されるようになり、その結果として在宅診療所や訪問看護ステーションの数も劇的に増えてきた。 現場感覚として、在宅診療への診療報酬はあまりにも過剰過ぎると感じている。 それでも、家で最期を看取るという在宅診療所における在宅看取り率は現時点で15%前後とこの20年間でほとんど増えていない。 そもそも「地域包括ケア」で目指していた在宅診療の根幹は、「24時間365日」「病院に行けない重症度の高い患者」を在宅において「看取りまで」介護従事者と連携をしながら最終的な責任を持って医療的ケアをしていくということにある。 ただ、その「本来あるべき在宅診療」は増え続けた診療所のほとんどにおいて全くできていない、というよりはやる気がなく、過剰な診療報酬を獲得するためだけにやっている在宅診療も少なくないとすら言える。
ふじみ野市の医師のように「本来の在宅診療」を真面目にすればするほど、日々ギリギリの緊張感のなかで患者やその家族と接し、その痛みや苦しみ、葛藤と向き合い続けることになる。 病院においては、ドクターをはじめとした医療従事者にとってのホームであるため、多少傲慢なドクターがいても「しょうがないわね、お医者様だから」となりがちだが、在宅診療ではそれは決して許されない。 患者のまさに「ホーム」であるため、患者やその家族には病院のような圧迫感や緊張感がなく、言いたいこと、言わなくてはならないこと、聞きたいことが気楽に伝えられる環境にある。 そのため、在宅診療側としては、病状だけでなく生活環境、介護体制、金銭面での不安、家族の看取りへの思いなど多様ないのちの周りにある幸せや痛みに寄り添い続けていくことが不可欠である。 特に、看取りが近い重症度の高い患者が多いという背景もあるため、家族と医療従事者のコミュニケーションのちょっとした掛け違いがふじみ野市のような事件になることもありうると言える。
国や地方自治体で「地域包括ケア」が謳われて15年以上が経過し、基礎的自治体における地域医療の計画策定が義務化され、形式的には訪問診療、訪問看護の事業所は増えてきた。 一方で、本来目的としていた「病院から地域へ」という患者が過ごす環境への政策誘導が成功してきたとは言えない。 在宅における看取り率は未だ15%前後であり、そもそも求められていた地域包括ケアが適切に機能しているとは到底言えない状況である。
「コロナ禍」という一つの大きな時代の変化を通じて、在宅診療の需要は明らかに高まってきた。 地域の中核病院が「コロナ病床」に変化せざるを得なかったため、それまで病院でケアされていた患者を重症度対応ができる在宅診療に移行してくるようになった。 癌末期などで入院している患者は、最後の時間を大切な家族や友人と病院や施設では面会できないため、過ごし慣れた自宅に戻って療養するという選択も増えてきた。 一方で、受け皿となる在宅診療の「質」の問題が大きな課題となっている。在宅看取り率が上がっていかない理由も在宅診療が単なる「往診する医師」となっていることに起因している。
昨今、医師のワークライフバランスが強調されることにより、在宅診療の分野においても「分業」が推奨される傾向がますます高まっている。 常勤医師と非常勤医師の分業、昼の担当医師と夜の担当医師の分業、定期訪問と緊急対応の分業、自宅患者と施設患者の分業、 本来、一人の患者に対してそのいのちや生活に医療機関として関わるうえでは分けられないもの、分けるべきではないものが、合理的な経営体制の持続のために分けられてしまっている。
24時間365日やっている形だけ作っている「なんちゃって在宅医療」があまりにも増えている。 その具体的な現状における問題を指摘する。
一つは、外来を土台にしながら在宅診療をうたうクリニックの問題である。 外来をしながら、訪問診療のために複数人の医師を24時間365日往診できるように体制を整えているならばなんの問題もない。 ただ、実際にはほとんどは外来を中心にしながら往診を片手間にして24時間体制を前提とした管理料をとっているクリニックが多いのである。 昔でいう地域の「かかりつけ医」が日常において往診に行くことはとても素晴らしいことであり、そのこと自体が「1次救急」の役割として重要であることはいうまでもない。 ただ、それは「たまたまの往診」であってはならず、在宅医療は「必ず往診に行く」でなくてはならない。 少ない医師で外来をしながら在宅診療を行う医療機関は、外来診察中は往診に行くことができないために、緊急時でも結局自院に訪問してもらうか、救急搬送での対応としてしまう。 夜間や土日も緊急での往診体制を前提とはしておらず、本来ならば契約時点で「24時間体制である」という在宅診療がその診療報酬をいただくための最低限の条件をきっちりと説明をしておらず、 緊急連絡先すらも渡していないという場合も見受けられる。
もう一つの問題は、「バイト型在宅診療」の広がりである。 他の医療と比べて診療報酬に圧倒的な優位性がある在宅診療において経営者として解決しなければならないのは、日中の往診できる医師の確保と夜間土日の体制整備である。 多くの在宅診療機関においては、大学などと連携して「週1回のアルバイト医師」を定期的に用いることで、医師不足を解消している。 また、土日や夜間においては「医療連携」「夜間救急の専門医療機関」などと耳障りのいい言葉を使いながら、複数医療機関の当直体制を一事業所や一つのコールセンターで請け負う医療機関が出てきている。
私たちの診療所では、開業してから日中も夜間も全て常勤医師が対応することを前提にしている。 日頃からそれぞれの患者を情報共有している常勤医師だけが夜間もローテーションで対応する。 「医師のワークライフバランスは?」という質問に対しては、それを乗り越えて患者の思いに答えるからこそ診療報酬で圧倒的に優遇されていると答えざるを得ない。 在宅診療は救急医療ではない。 日々の変化や患者やその家族の価値観がわからない医師が夜間に訪問しても、患者やその家族の意向に寄り添うことは絶対にできないし、 事情がわからない医師や楽をしたい緊急往診担当の医師は「すぐに救急搬送しましょう」ということになってしまう。 緊急時における常勤体制が土台にない診療所では、日々の変化に対して、バイト医師の出勤日以外には患者やその家族が日常的に主治医に対して相談できないことになる。 在宅診療は診療報酬が高いからこそ、本来はその環境整備、人的資源に投資をしなくてはいけないはずである。 質をあげることにその利潤を費やすのではなく、事業拡大として各地域に支部を拡大してし、クオリティの落ちる「看取りまでできない在宅診療所」が全国に広がるだけになっているのが現実なのである。 また、地域の中核病院や開業医がその報酬に目がくらみ、「片手間」に緊急往診体制を整えないままに見切り発車をして始めるケースも増えている。
「在宅診療」は、そもそも楽にできる医療ではない。 そして、その対応範囲も幅広くがんの末期への対応のなかで麻薬の管理から褥瘡に対する外科的な処置など、多様な専門性と医療技術が必要とされるものである。 「病院に通院できない状態」を前提として在宅診療となるので、病院と同じことが在宅でも当然のようにサポートできるとともに、病院以上に患者の思いに寄り添わなくてはならない。 専門的な医療技術とコミュニケーション能力、そして患者に継続して向き合える医療体制、本来求めるべき在宅医療を妥協せずに育てていくことが不可欠である。 まだまだ、在宅診療の実態や課題については、政治、地方行政、メディア、中核医療機関、そして地域住民の間でもまだまだ十分な理解はされていない。 だからこそ、真面目に行う医療機関と安易なフランチャイズのような経営をする医療機関の区別が十分にされずに患者側の「適切な選択」もできない状態にあるのである。 ふじみ野市の「真面目な在宅診療」に訪れた悲劇はしっかりとあるべき在宅診療の議論につなげていける大きなきっかけにしていかなくてはならない。
そのような課題があるなかで、具体的に「家で最期まで看取る環境」を作るためには何が必要なのだろうか。 そのような議論をする上で、必ず金銭的な条件や家族の負担ということが出てくる。ただ、それは決して大きな課題ではないと断言することができる。
私たちの患者の3割は生活保護世帯であり、行政側からその介護環境の改善も含めて在宅診療を依頼されることも少なくない。 在宅診療はあくまで「医療保険制度」の枠のなかで行われるものであり、在宅で酸素管理やその他重症度が高い方々へ必要な医療を提供したとしても、病院と比べて特別な費用負担がかかるわけではない。 かえって病院における差額ベッド代や高めの食事代を払ったりする必要がない分において、患者負担としての医療費は高くない。
また、家族の「介護的な負担」という意味においては、本来家族の負担を可能な限り減らすために訪問診療や訪問介護サービスが介入するものだと思っている。 もちろん、病院や施設に預けっきりになっている場合と比べて、「家族が関わる」ことが多いのは当然である。 それを「負担」と感じさせるかどうかは、医療や介護の質によるものである。 在宅でもしっかりと苦痛の緩和をし、夜間の不穏などのコントロールをすることによって、家族は「負担」と感じることは圧倒的に少なくなる。 もともとしている仕事をやめたりする必要もなく、重症度が高い方への食事や排泄の管理、入浴介助も介護職種がしっかりとその家族の環境に応じて調整することができる。 また、状況に応じてデイサービスやショートステイ、家族が休むためのレスパイト入院(※2)なども、医療・介護職種が積極的に家族とのコミュニケーションを取ることで充実して、負担を感じさせないサポートをしていけるのである。
その上で、これから「在宅看取り」の環境をこの国で進めていくために重要ではあるが、まだ十分ではない、解決していくべき方向性について話をする。
まず第1に、「住居環境」のあり方をしっかり整えることである。 医療や介護サービスを受けるにしても、日常生活を送るのに必要なスペースの確保や、セキュリティやバリアフリーや衛生状態が守られているかは自宅で最期まで過ごす上で欠かせないポイントである。 いくら病気を直しても衛生環境が悪いことで感染症を繰り返したり、生活保護を受けている患者が食事のためのお金が途中で切れて栄養失調になったり、冬場に暖房器具がなくて凍死しそうになる、そんな人はこの日本においても後をたたない。 行政に相談しても「保護費は渡してありますから対応できません」と現場も見に来ずに対応されることもある。 行政は、形式的な多職種連携会議を主催することよりも日々の地域における医療・介護機関からの情報に対して命や生活に対する迅速で柔軟な対応ができる組織形成を行うべきである。 住居環境が整うことで、不必要な緊急搬送や施設への入所をしなくとも、本人や家族にとって思いのある「自宅」で最期まで過ごせることに繋がるのである。
第2は医療のインフラ整備である。 これまでの医療体制は地域の中核病院と医師会を基軸とした制度設計がされてきたため、困ったら病院への搬送、重度の疾患のお看取りは病院でということが当たり前になっていた。 コロナ禍を背景にして、「在宅でできることは在宅で」という当たり前の感覚が医療の側面でも住民意識にも生まれてきている。 重症度の高い疾患に高度な医療の提供が在宅診療でもできる医師や診療所の育成を前提として、中核病院や介護関係職種の間で適切な情報共有をしながら、「地域全体で患者を支える」体制作りを中長期で行なっていくことが不可欠である。 各地域での需要が薄れている開業医や中核医療機関は思い切った在宅診療の体制への移行も検討していくべきであり、その移行を行政として支援していくことも今後検討していくべきである。 ただ、前段で述べたような「片手間」な在宅診療ではなく、本気で24時間体制で挑んでくれる医療が生まれることで地域は変わっていくことは間違いない。
第3は、介護とリハビリテーションの体制づくりである。 在宅で医療を受けたくても、どうしても家族の理解が得られない場合、または在宅診療や訪問介護などの人的な体制が地域で十分でない場合もありうる。 そのような地域においては、日常の生活の場として通所型サービス(デイサービスやデイケアなど)の事業所や、訪問介護を受け入れやすい高齢者向けのマンション(サービス付き高齢者向け住宅)などの整備が不可欠となる。 行政としては、地域の中で将来的にどれくらいの高齢者の需要が生まれるのかを詳細なデータのもとで予測した上で具体的な整備を進めていく必要がある。 長年に渡って、医療と介護の分野が情報共有をされないまま縦割りとなっていることも大きな問題であり、それをつなぐケアマネジャーを中心とした、現場での「患者のため」の調整機能が果たされていくことが重要であり、 行政としては地域でのそのような意識醸成のための研修会の開催なども大切である。 私たちは在宅診療として、どんな状態の患者でも「自宅看取り」ができるという自信のもとで仕事をしているが、家族や本人の選択肢として、「自宅以外」でも幸せな医療や介護が受けられる、そんな介護環境の整備をしていく必要がある。 家族の環境や病状の変化によって、どこで最期を迎えたいかという患者や家族の思いが変わることは当然のことである。 だからこそ、その柔軟な思いに寄り添える環境づくりを進めていくことが大切なのである。
第4は、予防という観点である。
自治体は地域支援事業によって介護予防プログラムなどを行っている。
そのようなプログラムへ積極的な市民参加を促すことで住民のADL(日常生活動作)や筋力の維持・向上を図ったり、地域社会の中で他人と接する機会をつくることで、生きる意欲の向上にもつなげることができる。
最近では、各自治体が高齢者の持つ技術や経験を生かして、住民に対する家事手伝いや軽作業といったサービスを提供する「シルバー人材活用」も以前よりも活発になっている。
平均寿命が伸び続けるなかで、退職後の高齢者の収入の確保も重要であり、短い時間で無理なく働ける仕組みを定着させることも介護予防につながることもあり、様々な行政としての工夫が必要となってくる。
高齢者を活用する民間企業の各種取り組みを支援するシステム構築も重要である。
第5としては、基本的な人としての「いのち」を守る生活支援である。 生活支援を必要とする人は、身寄りがない人、諸事情により家族と一緒に生活ができない人、経済面で問題のある生活困窮者など多岐にわたる。 医療の必要がない状態で、安否確認のための定期的な訪問から炊事や掃除などの生活支援まで、軽微なサポートだけで日常の暮らしが落ち着く人もおり、中長期における医療や頻回の介護介入を予防できることにもつながる。 生活支援のための人材育成はこれからの大きな課題であり、行政だけで解決できるものでは到底ない。 地域や民間企業の取り組みを把握しながら、単なる補助金行政に終わるのではなく、自治会など地域での取り組みや積極的な役割を果たす民間企業へのサポートが重要であり、 関わる人たちが誇りを持てるような体制づくりへの協力が必要である。
各自治体で「地域包括支援事業」は形としては行われているものの、実効性があるものは多くはなく、現実として多くの課題も見えてきている。
人口の多い都心部と過疎になりつつある地方とでは、地域包括ケアシステムのあり方も異なる。 地方による財源のばらつきもあるが、これまでのように頑張っている民間の努力に委ねるだけではなく、どこまで各自治体が「覚悟」を持った体制づくりに取り組めるかが重要である。 厚生労働省は地域包括ケアシステムを機能・継続させていくため、ボランティアの力にも期待しているというが、ボランティア人材を集めるにも地域格差の問題は無視できない。 これまで各地域で「認知症サポーター」が育成されても、実際には現場で活用されていない現実がほとんどであり、人材の育成だけでなく、その活用も現場にあわせて具体的に取り組んでいくべきである。 企業の多くは社会貢献活動に力を入れており、大学など教育機関も学生にボランティア活動を奨励している。 もし、地域に企業の事業所や大学の寮などがある場合、そのような主体に自治体、住民と連携した地域包括ケアシステムの重要性を理解してもらい、参画してもらうための啓発活動を展開していくことも考えられる。
ALSなど重症度の高い患者を24時間体制でサービスを提供できる事業者はかなり限定的であり、思いのある事業者がその体制をつくったとしても大きな赤字が生み出されるのが現状である。 私たちの医療法人が地域で求められる24時間介護の事業所をこの1月から作ったが毎月約300万円の赤字が続くのが現実である。 ただ、その必要とする方々にはしっかりと喜ばれている。 在宅診療での過剰すぎる利益をその事業に還元するから成り立っているに過ぎない。重症度の高い患者を在宅でフォローするためには、24時間体制での医療や介護のあり方やその報酬について具体的に整備していく必要がある。 繰り返しになるが、これまで在宅診療や訪問看護の事業所は優遇措置をとるなかでその数が増えてきたが、真摯に24時間体制でサポートする事業所の数があまりに少ない。 また、24時間の介護体制を保証する事業所への公的支援は弱く、まだ十分に必要な体制が行き渡っていない。 これからは、24時間と謳うだけの「形だけの在宅診療」を増やすのではなく、実効性のある公的な医療介護を提供できる主体を地域でしっかりとチェックをしながら育成していく必要がある。 一方で、国の制度を悪用して利益を享受する医療介護の事業体については厳しく排除をしていくべきである。 そのために、「看取りの実績」「人的な配置体制」などを監視しながら、それに応じた報酬体系をしっかり作るべきである。
全国各地でその地域性を生かした「地域包括ケアシステム」と名前をつけた取り組みはすすめられている。 ただ、地域包括ケアシステムは決して新たな画期的な取り組みではなく、日本に古くから根付いている「助け合い」の精神がベースにある現場での極めて地道な取り組みそのものである。 本来、行政主体であるべきものではないが、民間の自発性に任せていてはいつまでも「地域格差」も埋まらず、良質な医療介護体制も育っていかない。 まだまだ、在宅で誰もが当たり前の看取りができるという意識は地域で育っておらず、現実としてどの地域でもそのような体制が取れているわけでもない。 江戸川区、葛飾区、三重県四日市市などではたまたま「看取りまで責任を持つ医療機関」があることで、地域の介護環境全体も育成されてきた経過がある。 それぞれの自治体や各事業所の努力や思いに支えられるだけではなく、国が「看取りまで家で支えられる国の未来」へのビジョンをしっかりと描き、具体的なそれに向けた医療体制と、 地道にその足元を支える介護体制へのサポートについても覚悟を持って進めていく必要があるといえる。
- ※1 Dr.コトー…離島にある小さな診療所で働く医師の姿を描いた医療漫画『Dr.コトー診療所』の主人公。
- ※2 レスパイト入院…主に介護が必要な人々の家族や介護者に一時的な休息を提供するために実施される入院。
1976年三重県松阪市生まれ。
慶応義塾大学法学部法律学科、群馬大学医学部医学科卒業。
医師として、ケニアのHIV罹患率が40%を超える地域において現地の方々とともに巡回医療とHIV孤児支援のプロジェクトを立ち上げる。
南アフリカ、ジンバブエ、ウガンダなどアフリカ各地域で医師としてスラム地域などでの孤児支援や医療支援を行う。
2009年当時、全国最年少市長として松阪市長に就任。
松阪モデルとして「市民が役割と責任を持つまちづくり」が評価され、マニフェスト大賞最優秀賞を受賞。 また、ジュネーヴで行われた世界市長会議において日本代表として招聘。アエラの次世代を担う100人に選出。
また、松阪市民病院管理者として20年以上赤字の公営病院を黒字に転換する。
2期市長を務めた後、四日市市のいしが在宅ケアクリニックにて、重度の末期がんの患者を中心とした「看取り」までの在宅医療に従事。
その後、江戸川区で在宅医として勤務後、在宅医療・訪問看護を長年行なってきたメンバーとともに「しろひげ在宅診療所」を開設。
地域づくりや地域包括ケアなど全国各地で講演や自治体研修などを行う。